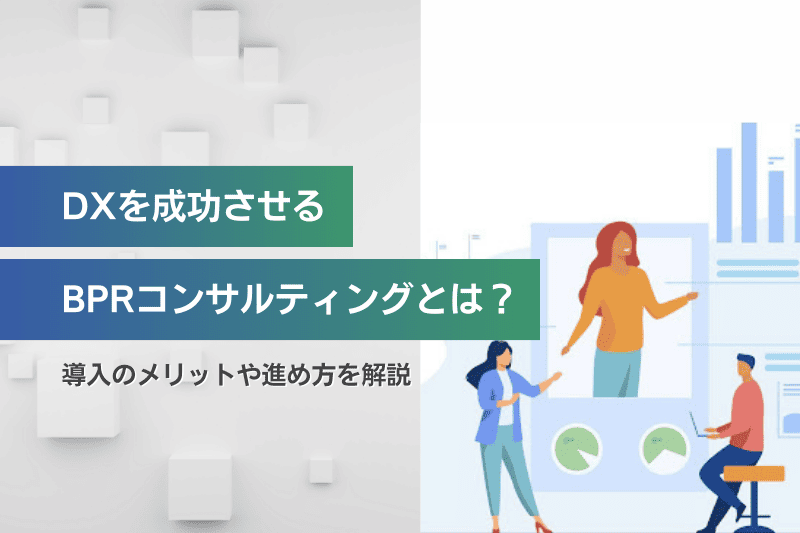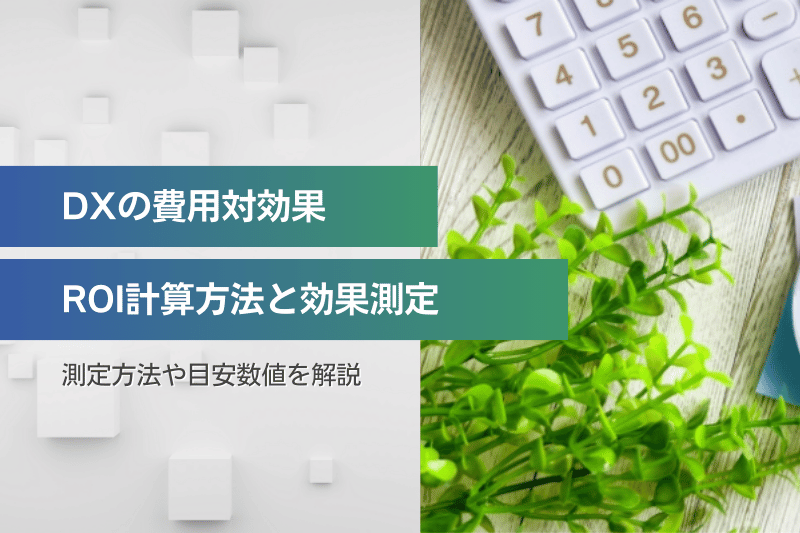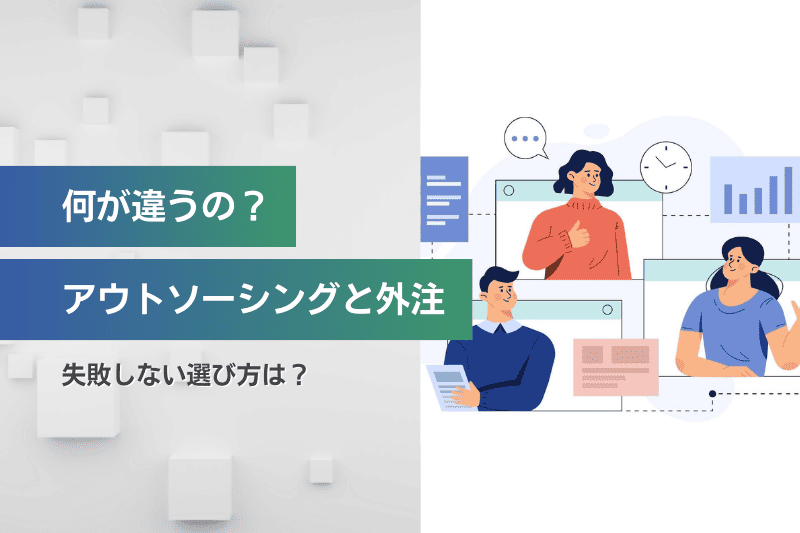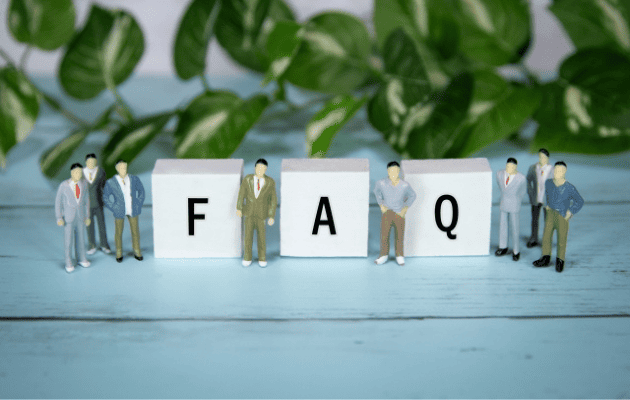システム開発のコストを抑える有効な手段として、海外のリソースを活用するオフショア開発が注目されています。
しかし、「言葉の壁が不安」「品質は大丈夫か」といった懸念から、導入に踏み切れない経営者も少なくありません。
DX(デジタルトランスフォーメーション)推進への投資は安価ではなく、失敗すれば企業の成長に大きなブレーキをかけてしまいます。だからこそ、リスクを正しく理解し、適切な対策を講じることが重要です。本記事では、オフショア開発に潜むリスクと回避するための実践的なノウハウを解説します。漠然とした不安を解消し、貴社のシステム開発を成功に導くための判断材料としてお役立てください。
記事監修者

DX開発パートナーは、20年以上の実績を持つリーダーを中心に、
多様なバックグラウンドを持つ若手コンサルタント、PM、エンジニアが連携するチームです。
柔軟で先進的な発想をもとに、DXの課題発見からシステム開発・運用までを一貫して支援しています。クライアントの「DX・システム開発」に関する課題やお悩みをもとに、役立つ情報を発信しています。
オフショア開発の現状とリスクを理解すべき理由

国内のIT人材不足が深刻化する中、多くの日本企業が開発拠点を海外に求めているのです。
かつては「コスト削減」が主目的でしたが、現在は優秀なエンジニアを確保するための「リソース確保」へと目的が変化しつつあります。
しかし、海外での開発には国内とは異なる特有のリスクが存在します。
リスクを事前に把握しコントロールできれば、オフショア開発は強力な武器になります。まずは現状とリスク管理の重要性を正しく理解することから始めましょう。
なぜオフショア開発で「リスク管理」が成功の鍵を握るのか?
システム開発において、リスク管理はプロジェクトの成否を分ける最も重要な要素です。
特にオフショア開発では、物理的な距離や文化の違いがあるため、問題が発生した際の対応が遅れがちになります。
もしリスク管理を怠れば、バグの修正や仕様の変更といった「手戻り」が頻発します。手戻りが発生すると、修正のための追加費用や時間がかかり、当初見込んでいたコストメリットが消えてしまうでしょう。
利益率や回収期間を比較し、限られた資金を有効に配分するためにも、リスクによる損失を計算に入れる必要があります。
リスクを未然に防ぐ仕組みを作ることが、高い費用対効果(ROI)を実現するための近道です。
2025年以降の最新トレンド:円安や人件費高騰によるリスクの変化
近年の急激な円安や、新興国の経済成長に伴う人件費の高騰により、オフショア開発のコスト構造は大きく変化しています。
かつてのような「圧倒的な安さ」だけを求めて開発を依頼するのは難しくなってきました。
JETRO(日本貿易振興機構)の「2023年度 海外進出日系企業実態調査」によれば、2024年の昇給率見通しにおいて、ベトナムは5.8%、インドは9.4%など、主要国での賃金上昇率が高止まりしている現状が浮き彫りになっています。
エンジニアの単価が上昇傾向にあるため、単にコストを下げることだけを目的にすると、期待通りの成果が得られない可能性があります。
今後はコストだけでなく、「高度な技術力」や「開発スピード」といった付加価値を重視する必要があるのです。
市場の変化を見極め、どの国のどの企業とパートナーシップを組むかが、ビジネスの成長を左右するでしょう。
必ず押さえるべき「オフショア開発の主なリスク」7選
オフショア開発を成功させるためには、どのような落とし穴があるのかを具体的に知っておく必要があります。
漠然とした不安を明確な課題として認識することで、適切な対策を打てるようになるからです。
代表的なリスクとして、以下のリスクが挙げられます。
- コミュニケーションの壁と認識の齟齬
- 品質管理の難しさと納品物のクオリティ低下
- 納期遅延と進捗管理の不透明化
- セキュリティ・情報漏洩への懸念
- 知的財産権(IP)や契約に関するトラブル
- 想定外のコスト増加
- 地政学リスクとカントリーリスク
オフショア開発で特に注意すべき7つの主要なリスクについて、詳細に解説します。
コミュニケーションの壁と認識の齟齬
海外のエンジニアと協業する際、最大の壁となるのが言語と文化の違いによるコミュニケーションの問題です。
日本語が話せる現地の担当者がいたとしても、細かなニュアンスまで正確に伝わるとは限りません。
例えば、発注側が「言わなくても分かるだろう」と考えていることでも、開発側には全く伝わっていないケースが多く存在します。
日本のビジネス現場に特有の「阿吽の呼吸」や「空気を読む」文化は、海外では通用しないと考えるべきです。
認識のズレを放置したまま開発が進むと、完成したシステムが思っていたものと違うという事態に陥ります。
小さな誤解が積み重なり、最終的に大きな手戻りコストを発生させる原因となるのです。
品質管理の難しさと納品物のクオリティ低下
日本と海外では、品質に対する意識や基準が異なる場合があります。
日本人が当たり前と感じる「使いやすさ」や「見た目の美しさ」といった感覚的な品質は、明確に指示しない限り重視されないことが多いです。
「直感的に使えるシステムを」といった曖昧な要望では、機能としては動作しても、現場では使いづらい仕上がりになる場合があります。
仕様書に書かれていない部分は、開発側の独自の判断で作られてしまうからです。
どのような品質を求めるのかを明確にし、開発プロセスの中で確認する仕組みがなければ、品質をコントロールできません。
品質基準のすり合わせ不足は、納品後のトラブルに直結する深刻なリスクです。
納期遅延と進捗管理の不透明化
開発の全工程を現地に任せきりにしてしまうと、プロジェクトの進捗状況が見えにくくなるというリスクがあります。
現地の文化によっては、問題が発生していても直前まで報告が上がってこないことがあります。
定期的な報告の場を設けていないと、「順調です」という言葉を信じるしかなく、状況を正確に把握できません。
結果、納期の直前になって「実は終わっていない」と報告される最悪の事態を招きます。
プロジェクトの進捗を可視化する仕組みがない丸投げは、納期遅延のリスクを常に抱えています。物理的な距離があるからこそ、国内開発以上に頻繁な確認と管理が必要です。
セキュリティ・情報漏洩への懸念
システム開発では、顧客情報や機密データを扱うため、情報漏洩は企業の信用に関わる重大なリスクです。
開発会社が国際的なセキュリティ基準を取得していたとしても、個々の担当者の意識まで高いとは限りません。
外注先の管理が甘いと、サイバー攻撃だけでなく、内部の人間による不正な持ち出しのリスクも高まります。
特にオフショア開発においては、IPAの「情報セキュリティ10大脅威 2024」でも指摘されている通り、サプライチェーンの脆弱性を突いた攻撃が深刻化しています。
特に海外では、データの取り扱いに関する法的規制や商習慣が日本とは異なる場合があるのです。現地のセキュリティ環境やデータの管理体制について、契約前に厳重にチェックする必要があります。
知的財産権(IP)や契約に関するトラブル
開発されたシステムやソースコードの権利が誰に帰属するかは、後々のトラブルの原因となりやすいポイントです。
国によっては、著作権や知的財産権に関する法律が日本とは大きく異なる場合があります。日本の常識で契約を進めてしまうと、法的な保護が十分に受けられず、不利な立場に立たされるかもしれません。
例えば、契約書に明記がない場合、開発会社側が著作権を主張し、自社で自由に改修できなくなる恐れがあります。
この場合は、どの国の法律を基準にするかを決める手続きが不可欠となります。日本の法律を選ぶのか相手国の法律を採用するのか、契約を結ぶ前に確定させておきましょう。
一般的には日本の法律が優先されますが、現地の企業から自国の法律を適用したいと提案される場面もあります。
不測の事態を防ぐためにも、双方が納得できる条件を丁寧に見つける作業が大切です。
想定外のコスト増加
コスト削減を期待してオフショア開発を選んだにもかかわらず、結果的に高くついてしまうことがあります。
なぜなら、目に見える開発費以外の「隠れコスト」を見落としている場合が多いからです。
例えば、コミュニケーション不足による手戻りが発生すれば、修正のための追加費用がかかります。
また、現地への渡航費や、通訳・翻訳にかかる費用、日本側の管理工数なども考慮しなければなりません。
費用対効果を計算する際は、費用の見積もりを正確に把握することが重要です。
初期費用だけでなく、運用費や人件費も含めた「総投資額」で判断しなければ、正しいROIは算出できません。
地政学リスクとカントリーリスク
オフショア開発特有のリスクとして、対象国の政治情勢や自然災害、インフラの不安定さが挙げられます。
急な政権交代やデモ、紛争などが発生すれば、開発業務が完全にストップしてしまう可能性があります。
また、電力供給が不安定な地域では、計画停電や通信障害によって作業が遅れることも珍しくありません。
日本とは異なる祝日や宗教的な行事(ラマダンなど)も、スケジュールに影響を与える要因となります。
一国に集中して開発拠点を置くと、その国のリスクを全面的に被ることになります。万が一の事態に備え、リスク分散の観点から複数の国や拠点を持つことも検討すべきでしょう。
オフショア開発のリスクを最小限に抑えるための対策

ここまでに挙げたリスクは、適切な対策を講じることで大幅に低減させられます。
「丸投げ」をせず、外部のプロと協力して事業を成功させる「戦略的パートナーシップ」と考えることが重要です。
発注者側が主体性を持ってプロジェクトに関わることで、失敗の確率は劇的に下がります。
以下、4つのオフショア開発のリスクを最小限にする対策を紹介し、それぞれを解説します。
- ブリッジSE(BrSE)の選定と役割の明確化
- アジャイル開発の導入による「早い段階での軌道修正」
- 仕様書の徹底したドキュメント化と「図解」の活用
- 強固なセキュリティ環境の構築と秘密保持契約(NDA)
ブリッジSE(BrSE)の選定と役割の明確化
日本側と現地エンジニアの間に入り、橋渡し役となる「ブリッジSE」の存在は極めて重要です。
彼らは単なる通訳ではなく、ビジネスの要件を技術的な仕様に翻訳して伝える役割を担います。
優秀なブリッジSEがいれば、言葉の壁を超えて正確な指示を出し、認識のズレを防ぐことができます。
選定の際は、日本語能力だけでなく、日本のビジネス習慣や開発プロセスへの理解度を確認しましょう。
また、ブリッジSEに任せきりにせず、自社の担当者とも密に連携を取れる体制を作ることが大切です。コミュニケーションのハブとなる人材の質が、プロジェクトの円滑な進行を左右します。
アジャイル開発の導入による「早い段階での軌道修正」
要件を最初に全て決めてから開発するのではなく、短いサイクルで開発と確認を繰り返す「アジャイル開発」の導入が有効です。
実際に動くソフトウェアをこまめに確認することで、認識の齟齬を早期に発見できます。
仕様に関する小さな疑問や確認事項は日々発生するため、すぐに解消できる環境が必要です。
1〜2週間ごとに成果物を確認すれば、万が一方向性が違っていても、最小限の修正コストで済みます。
こまめにデモを確認することは、発注者側がプロジェクト管理をする上で最低限すべき行動の一つです。完成直前での大きな手戻りを防ぎ、実用性の高いシステムを作り上げることができます。
仕様書の徹底したドキュメント化と「図解」の活用
言葉での説明だけでは伝わりにくいニュアンスを補うために、詳細なドキュメントと視覚的な情報を活用しましょう。
画面の遷移図やワイヤーフレームなど、図解を多用することで、言語の壁を越えた理解が可能になります。
ボタンの配置やデータの表示方法といった細かい仕様についても、図で示すことで誤解の余地を減らせます。
さらに、ドキュメントは常に最新の状態に保ち、決定事項は必ず記録に残すことが大切です。
「言った言わない」のトラブルを防ぐためにも、仕様書は契約の根拠となる重要な資料です。手間はかかりますが、丁寧な資料作成が結果として開発効率を高め、品質の向上につながります。
強固なセキュリティ環境の構築と秘密保持契約(NDA)
情報漏洩リスクに対抗するためには、物理的な対策と法的な対策の両輪が必要です。
開発環境へのアクセス権限を厳格に管理し、不要なデータの持ち出しができないような技術的な制限を設けましょう。
例えば、VDI(仮想デスクトップ)を導入し、現地の端末にデータを保存させないといった対策が有効です。
また、開発会社とは必ず秘密保持契約(NDA)を締結し、違反時のペナルティを明確にする必要があります。
信頼できる開発会社は、ISMS認証などのセキュリティ基準を取得し、情報を厳重に管理しています。
契約前にセキュリティ体制をチェックシートなどで確認し、不安要素を取り除いておきましょう。
国別に見るオフショア開発のリスクと特徴の比較

オフショア開発の委託先として選ばれる国には、それぞれ異なる特徴とリスクがあります。
自社のプロジェクトの性質や予算、求める品質に合わせて、最適な国を選ぶことが成功への第一歩です。
ここでは、主要なオフショア開発国であるベトナム、フィリピン、インドネシア、中国の4カ国について、その特徴と留意すべきリスクを比較解説します。
ベトナム:親日度が高く人気だが、人件費上昇と離職率に注意
ベトナムは親日的な国民性を持ち、勤勉なエンジニアが多いことから、現在日本企業に最も人気のあるオフショア先の一つです。
政府がIT教育に力を入れており、若くて優秀な人材が豊富に供給されています。
しかし、人気が集中しているため、近年は人件費が上昇傾向にあります。
また、エンジニアの流動性が高く、より良い条件を求めて短期間で転職してしまう「ジョブホッピング」のリスクには注意が必要です。
プロジェクトの途中で主要なメンバーが抜けると、引き継ぎに時間がかかり進捗に影響が出ます。
長期的な体制維持のためには、定着率の高い開発会社を選ぶか、人材のリテンション対策を確認しておきましょう。
フィリピン:英語力とホスピタリティが魅力だが、インフラ面に懸念
フィリピンの最大の魅力は、英語が公用語であり、コミュニケーションがスムーズな点です。
欧米文化の影響を受けているため、デザインやUI/UXの感覚も比較的日本や欧米に近いものを持っています。
一方で、台風などの自然災害が多く、電力や通信といったインフラ面での脆弱性が懸念されます。停電やネット回線の不具合によって、開発作業が一時的にストップするリスクを考慮しなければなりません。
明るくフレンドリーな国民性は魅力ですが、納期に対する意識が日本人ほど厳格でない場合もあります。
インフラのバックアップ体制が整っている会社を選び、進捗管理を丁寧に行うことが重要です。
インドネシア:豊富な若年層と市場成長性が魅力だが、宗教と文化の配慮が必要
インドネシアは東南アジア最大の人口を抱え、IT市場も急速に成長しています。
親日国であり、若くて意欲的なエンジニアが増えていることから、将来的なポテンシャルの高いオフショア先として注目されています。
注意点としては、イスラム教徒が多いため、宗教的な習慣への配慮が必要なことです。特にラマダン(断食月)の期間中は、業務効率が落ちたり、休暇取得が増えたりする可能性があります。
文化的な背景を理解し、スケジュールに余裕を持たせることがトラブル回避につながります。
また、法制度や税制が複雑な場合があるため、現地の事情に詳しいパートナーと組むことが推奨されます。
中国:圧倒的な技術力とスピードだが、コスト増と地政学リスクを考慮
中国はオフショア開発の歴史が長く、高度な技術力と豊富な実績を持っています。
地理的に近く時差も少ないため、日本企業との連携がしやすい点がメリットです。漢字文化圏であるため、仕様の理解も早いです。
しかし、近年は人件費が大幅に高騰しており、コストメリットは薄れています。また、カントリーリスクや政治的な緊張関係がビジネスに影響を与える可能性も否定できません。
単純な開発案件よりも、AIやビッグデータといった高度な技術を要するプロジェクトに向いています。コストよりも技術力やスピードを最優先する場合に、有力な選択肢となるでしょう。
よくある質問(FAQ)|オフショア開発のリスクを回避したい方々の声に回答

Q1. リスク対策にお金をかけると、国内の開発より高くなりませんか?
A1. 管理を徹底することで、最終的な総コストは国内より低く抑えられます。
初期の見積もりだけでなく、修正作業や意思疎通の手間を含めた全体予算で考える必要があります。
例えば、指示のズレで作り直しが発生すると、安いはずの開発費が大幅に膨らむのです。 管理体制を整える費用は、不要な出費を防ぐための保険のような役割を果たします。
結果的に品質の高いシステムが予定通りに完成して、投資に対する効果を最大化できます。
Q2. 優秀なブリッジSEを見極めるために、何を確認すべきですか?
A2. 言葉の壁を越えるだけでなく、日本の商習慣や技術的な背景を理解しているかを確認します。
自社の要求をそのまま伝えるのではなく、現地の文化に合わせて翻訳して伝える能力が求められます。
見極め方法として、過去にトラブルが起きた際、どのように現場を動かして解決したかを具体的に質問してください。
また、進捗状況を数字や図で論理的に説明できるかも、重要な判断基準となります。 技術と調整力の両方を兼ね備えた人材を選ぶことで、プロジェクトの成功率は飛躍的に高まります。
Q3. 日本と同等の品質を保つために、発注側ができる対策はありますか?
A3. 「動くかどうか」だけでなく、使い勝手や詳細な動作条件を事前に数値で示す必要があります。
日本と海外では、品質に対する考え方や「当たり前」の基準が異なるからです。
「使いやすくしてほしい」という曖昧な表現ではなく、具体的な操作手順や反応時間を指定します。
短い期間で成果物を確認したり修正したりする、こまめなレビューを繰り返してください。 基準を明確にして共有し続けることで、現地のエンジニアも求める品質を正確に理解します。
Q4. 海外拠点への情報漏洩を防ぐための、最も効果的な対策は何ですか?
A4. 秘密保持契約(NDA)の締結と、現地の物理的なセキュリティ管理状況を把握することです。
契約書に違反時の損害賠償額を明記することで、強い抑止力が働きます。
また、開発に使用するパソコンの持ち出し制限や、アクセス権限の厳格な設定を相手に求めましょう。
定期的に開発現場の様子をビデオ会議で確認したり、セキュリティ報告書を提出させたりします。 仕組みとルールの両面から対策を講じることが、企業の重要な資産を守るために不可欠です。
Q5. 従業員が少ない中小企業でも、オフショア開発を依頼するメリットはありますか?
A5. 国内でエンジニアを採用する手間やコストを省き、迅速に開発体制を整えられます。
中小企業は社内にIT専門家が不足している場合が多く、外部の豊富なリソースが大きな力となります。
大企業のような大規模予算がなくても、必要な機能に絞って段階的に開発を進めることが可能です。
自社の課題に寄り添って、戦略面から相談に乗ってくれるパートナーを選びましょう。
Q6. 開発したシステムの所有権やソースコードは、自社のものになりますか?
A6. 契約を結ぶ段階で、知的財産権が自社に帰属することを明文化する必要があります。
あいまいにしたまま進めると、後から追加のライセンス料を請求されたり流用されたりします。
特に、開発会社が保有する既存のプログラム部品の扱いについても、合意が必要です。
ソースコード一式を納品してもらい、自社で管理できる状態にすることを条件に入れてください。
権利関係をクリアにすることで、将来的なシステムの改修や他社への連携が自由に行えます。
Q7. アジャイル開発とウォーターフォール開発、どちらの手法が失敗しにくいですか?
A7. オフショア開発では、少しずつ成果を確認できるアジャイル開発の方がリスクを抑えられます。
仕様を一度に決めて進める手法では、最後に大きな認識のズレが発覚する恐れがあるからです。
短い周期で開発と検証を繰り返したり、フィードバックを行ったりすることで、軌道修正が容易になります。
進捗が見えやすくなるため、遠く離れた海外拠点との連携においても安心感を得られます。
状況に合わせて柔軟に計画を変更できる手法を選び、着実に目標へ近づく体制を構築しましょう。
Q8. 納品後のシステム保守や運用も、同じ海外の会社に任せても大丈夫ですか?
A8. 開発内容を最も理解している同じ会社に継続して任せることで、運用の安定性が高まります。
別の会社に引き継ぐ手間がかからず、不具合が発生した際も迅速な原因究明と対応を期待できます。
ただし、保守運用の費用や体制、対応可能な時間帯については、別途契約で定める必要があるのです。
夜間や休日のサポートが必要な場合は、あらかじめ現地の勤務体制を確認してください。
信頼できるパートナーと長く付き合うことで、システムの成長を長期的に支える基盤が整います。
まとめ|オフショア開発のリスクと回避策
本記事では、オフショア開発の現状から7つの主要リスク、具体的な回避策まで解説しました。
オフショア開発の成功は単なるコスト削減の手段ではなく、「戦略的なリスク管理」と「強固なパートナーシップ」の構築こそが本質なのです。
コミュニケーションや品質、セキュリティなど、海外特有の課題は確かに存在しますが、適切なブリッジSEの選定やアジャイル手法の導入で、リスクは克服可能です。
7つのオフショア開発で特に注意すべき主要なリスク
- コミュニケーションの壁と認識の齟齬
- 品質管理の難しさと納品物のクオリティ低下
- 納期遅延と進捗管理の不透明化
- セキュリティ・情報漏洩への懸念
- 知的財産権(IP)や契約に関するトラブル
- 想定外のコスト増加
- 地政学リスクとカントリーリスク
4つのオフショア開発のリスクを最小限にする対策
- ブリッジSE(BrSE)の選定と役割の明確化
- アジャイル開発の導入による「早い段階での軌道修正」
- 仕様書の徹底したドキュメント化と「図解」の活用
- 強固なセキュリティ環境の構築と秘密保持契約(NDA)
経営者にとって、迅速なIT化は生き残りをかけた重要課題です。 海外のリソースを賢く使いこなし、投資対効果を最大化させる必要があります。
情報の多さに惑わされず、自社の課題と向き合い、根拠を持って判断してください。
さらに、オフショア開発会社を調べたい方は、こちらで2026年版のおすすめオフショア開発会社が確認できますので、併せてご覧ください。
自社のケースを深堀して相談したい場合は、ぜひ専門家への問い合わせをご検討ください。
正しい知識と備えがあれば、オフショア開発は貴社の飛躍を支える最強の武器となります。 まずは小さな一歩から始め、理想的なデジタルの未来を切り拓いていきましょう。