
Buerger Consulting Inc.
Professional&
Navigator

お客様の真の右腕を
目指して
ビュルガーコンサルティングは、
高い専門知識・スキル・経験をもったプロフェッショナル集団として
お客様の抱えている問題を、解決へとナビゲートします。
Service
各領域に特化したコンサルティングを行っており、
今後もこの領域をコアコンピテンシーとして拡大強化を図っていきます。





株式会社アウナラ様にご紹介いただきました
調剤薬局特化型M&A仲介会社 株式会社アウナラの運営するコラム内の記事「迷ったらココ!人気のコンサルティング会社まとめ」に当社が掲載されました。
会社ホームページ:株式会社アウナラ
記事はこちら:迷ったらココ!人気のコンサルティング会社まとめ」
Columns
現役コンサルタントが業務、ITに役立つ情報を発信中
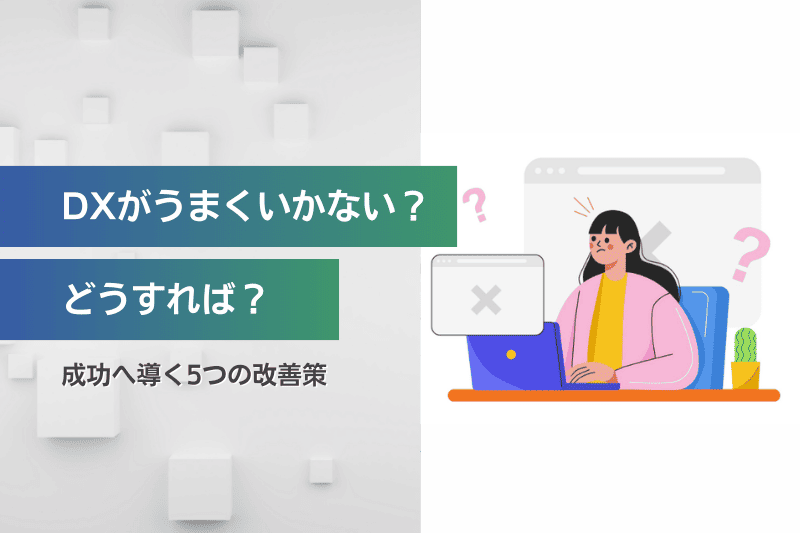
なぜDXはうまくいかない?現場が疲弊する「失敗理由」と打開策
「DXを推進しなければ」と頭ではわかっていても、「なかなか進まない」「投資に見合う効果が見えない」という悩みを抱える中小企業の経営者やIT担当者の方は非常に多いのではないでしょうか。
特に、情報過多の時代において、どの情報が自社にとって合理的で正しいのか判断に迷うこともあるかもしれません。
DXは単なるデジタル技術の導入ではなく、ビジネスモデルや組織文化を根本から変革することを意味します。
しかし、社内に専門人材が不足する中で、その変革への道筋が見えないことが、多くの中小企業の共通課題となっているのです。
本記事では、皆様のDXプロジェクトが停滞してしまう本質的な「壁」と「失敗理由」を徹底的に分析し、成功へと導くための具体的な5つの改善策を合理的な根拠に基づいて解説します。
この記事を読むことで、自信を持ってDXの実現に向けた計画を立て、次の正しい一歩を踏み出せるようになるでしょう。
記事監修者

DX開発パートナーは、20年以上の実績を持つリーダーを中心に、
多様なバックグラウンドを持つ若手コンサルタント、PM、エンジニアが連携するチームです。
柔軟で先進的な発想をもとに、DXの課題発見からシステム開発・運用までを一貫して支援しています。クライアントの「DX・システム開発」に関する課題やお悩みをもとに、役立つ情報を発信しています。
DXがうまくいかない正体:技術ではなく「組織」の病巣

多くの企業がDXを始めようとしたときに、まず立ちはだかるのが、社内構造や企業文化に根差した「見えない壁」です。
社内構造や企業文化の壁は技術的な問題というよりも、主に組織的な要因によって生まれます。
中小企業がDX推進のスタートラインに立つこと自体を難しくしている、主要な4つの障壁について詳しく解説します。
- 経営層の理解不足と優先度の低さ
- 社内のIT人材不足やスキルギャップ
- 既存業務文化や抵抗による変化の停滞
- データやシステムの統合が進まない
経営層の理解不足と優先度の低さ
DXが停滞する最も大きな要因は、経営層がDXを「一時的なIT投資」と誤解し、その本質的な戦略的価値を理解できていない点にあります。
結論から申し上げると、DXはIT部門の改善ではなく、全社的な経営戦略そのものだからです。
経営層が「なぜ今DXが必要なのか」「DXで会社をどう変えたいのか」という明確なビジョンを示せないと、現場は単なる作業として捉えてしまい、積極的な協力が得られません。
目先の利益を優先してDXの優先度が低いままだと、リソースや予算が十分に確保されずにプロジェクトが形骸化してしまいます。
経済産業省の「デジタルガバナンス・コード3.0」によれば、経営層こそが、DXを「生き残りと成長のための最重要課題」として位置づけ、強いコミットメントを示すことが、すべての変革の出発点となります。
社内のIT人材不足やスキルギャップ
中小企業にとって、DXの推進を担う専門人材の不足は、導入を阻む最も現実的な壁です。
ITリテラシーが中程度であっても、戦略を立案し、外部ベンダーの提案を評価・判断できる「デジタル人材」は圧倒的に不足しています。
この問題の理由は、専門知識を持つ人材の採用が難しく、育成にも時間がかかるためです。
その結果、外部パートナーに依頼したとしても、自社の課題を正確に伝えたり、提案内容の合理性を評価したりする能力が社内になく、丸投げによる失敗のリスクが高まります。
外部のプロの力を借りつつも、まずは社内担当者が主体的に関わり、ノウハウを蓄積する体制づくり、そして外部の知見を適切に活用できるスキルセットを身につけることが求められます。
既存業務の変化への抵抗による停滞
新しいデジタル技術を導入しても、実際に使う現場の従業員から抵抗感が生じることは珍しくありません。
DXが技術的な問題ではなく、既存業務への執着や企業風土の問題であることに起因しています。
長年培ってきた「このやり方が一番効率的だ」という習慣や慣習を変えることへの心理的な抵抗感は、想像以上に大きな壁となるのです。
この抵抗感は、特に従業員に対してDXの必要性やメリットが丁寧に説明されていない場合に顕著になります。
結果として、せっかく導入したシステムが使われずに放置されたり、新しいシステムに合わせて業務を変えることを拒否されたりして、変革の取り組み自体が停滞してしまうのです。
経営層が全社的な意識改革を主導し、丁寧なコミュニケーションを重ねることが必須となります。
データやシステムの統合が進まない
DXの成功は、部門ごとに散在するデータを一元的に管理し、部門横断で活用できる体制にかかっていますが、既存のデータやシステムの複雑さが大きな壁となります。
結論として、過去に導入されたシステム同士が連携できない「システムのサイロ化」が、データ活用を妨げていることが主な理由です。
特に中小企業では、古いシステム(レガシーシステム)が残っているケースが多く、そのデータ移行やシステム連携に莫大なコストや技術的な課題が発生します。
データがバラバラのままだと、経営層はリアルタイムで正確な経営状況を把握できず、合理的な意思決定ができなくなってしまいます。
データ活用を前提としたDXを進めるためには、まず自社の既存システムを客観的に棚卸し、統合に向けた戦略を立てることが重要です。
DX導入が失敗する理由
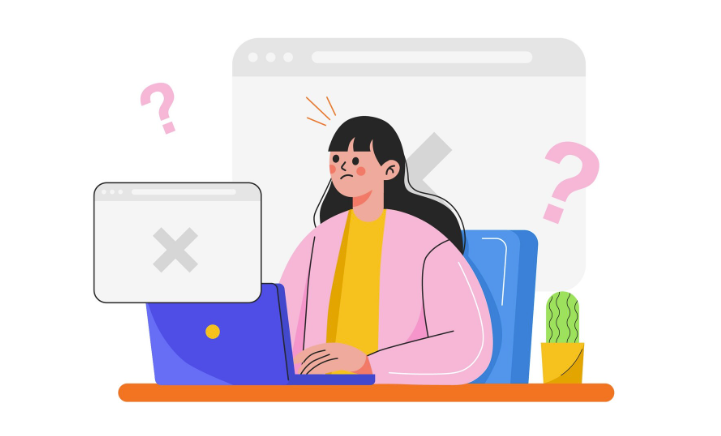
DXの導入を決定し、いざプロジェクトがスタートした後も、多くの企業が「進め方」の誤りによってつまずいてしまうのです。
プロジェクトを失敗に導く進め方に関する4つの典型的な理由と、避けるための具体的な視点について解説します。
技術的な要素だけでなく、戦略やプロセスに目を向けることが、失敗を避けるための鍵となります。
- 目的や効果が不明確なまま進める
- 技術導入だけに偏り、業務改善が伴わない
- パイロット導入を行わず全社一斉に進める
- 効果測定や改善プロセスが欠けている
目的や効果が不明確なまま進める
DXを失敗させる最大の原因は、「何のためにDXをするのか」という目的が曖昧なまま、手段であるデジタル技術の導入だけを急いでしまうことです。
なぜなら、「DX=流行りだからやるもの」という誤った認識が根底にあるからです。
具体的な数値目標や、達成後の状態が定義されていないと、プロジェクトは途中で方向性を失い、費用対効果(ROI)の検証もできなくなります。
例えば、「クラウドを導入する」ことが目的になり、「売上を〇パーセント向上させる」というビジネス目標が見失われてしまうのです。
技術導入だけに偏り、業務改善が伴わない
DXを「RPAやSaaSを導入すること」だと誤解し、技術の導入そのものに満足してしまうケースも、プロジェクト失敗の典型例です。
結論として、デジタル技術はあくまで「道具」であり、道具を活かすための「業務プロセス」や「組織文化」の変革が伴わなければ意味がないからです。
例えば、高性能なAIツールを導入しても、使用データが古かったり、現場の担当者がツールの機能を理解せずに従来の非効率なやり方を続けていたりすれば、何の成果も生みません。
業務の現状分析や新しいプロセスへの設計が不足していることに起因します。
技術導入だけに偏らず、導入によって業務フローをどう変え、誰が何をやるのかという業務改善(BPR)をセットで考えることが、DXの成功には必須となります。
パイロット導入を行わず全社一斉に進める
高額な費用と時間をかけて開発した新しいデジタルシステムを、いきなり全社的に導入しようとすることも、大きな失敗につながる理由の一つです。
その理由は、大規模なシステム導入は予期せぬ不具合や現場からの強い抵抗を生み出す可能性が非常に高いからです。
不具合が発生した場合、全社的な業務が停止する致命的なリスクも伴います。
合理的な回避策は、特定の部署や業務範囲に限定して導入する「パイロット導入(スモールスタート)」です。
小さく試すことで、システムやプロセスの問題点を早期に発見し、成功体験を積み重ねながら段階的に展開できます。
全社一斉導入という高リスクな進め方を避け、検証と学習を繰り返すアプローチが失敗を避けるための合理的な方法です。
効果測定や改善プロセスが欠けている
DXは一度変革したら終わりではなく、継続的に効果を測定し、改善を続けるサイクルがなければ、すぐに陳腐化してしまいます。
失敗する企業の多くは、システムを導入した時点でプロジェクトが終了したと見なしてしまうからです。
「DXの費用対効果は測れない」というのは誤解であり、事前に設定したKPI(重要業績評価指標)に基づき、売上向上、コスト削減、顧客満足度、従業員満足度などの項目を具体的に測定することが可能です。
測定の結果、目標が達成できていない場合は、システムの機能や運用方法、あるいはビジネスプロセスそのものを見直す「振り返り」が必要になります。
この効果測定と改善のサイクルが欠けていると、投資が単なる無駄なコストとなってしまうリスクがあるのです。
DX導入を成功させるポイント

DXの導入を阻む「壁」と、プロジェクトの「失敗理由」を理解した上で、いよいよ成功へと導くための具体的な5つのポイントを解説します。
- 経営層から現場までの共通理解を作る
- 解決すべき課題と目的を明確にする
- 小さく試して成果を見える化する
- 社員教育・コミュニケーションを重視する
- 効果測定と改善サイクルを回す
合理的な根拠を持って自信を持って推進できるよう、実践的な行動指針をご提示します。
これらのポイントは、大企業だけでなく、リソースが限られた中小企業こそ意識すべき、成功のための鍵となるのです。
経営層から現場までの共通理解を作る
DXを成功させるための最も重要な前提条件は、経営層と現場が同じ方向を向いていることです。
経営層がまず「DXによって会社がどう変わるか」という具体的で情熱的なビジョンを明確に提示する必要があります。
このビジョンは、単なるスローガンではなく、「5年後に市場シェアを〇%拡大するために、顧客データを活用する」といった具体的な目標に裏打ちされたものでなければなりません。
その上で、現場に対しては「この変革はあなたの仕事を奪うものではなく、より創造的で価値の高い業務に集中するためのものだ」というメリットを丁寧に伝え、変革への当事者意識を促すことが大切です。
上層部から現場まで、すべての階層で共通の理解を作り出すことが、DX推進の基盤となります。
解決すべき課題と目的を明確にする
DXの取り組みを始める前に、必ず「何を解決したいのか」という課題と、「何を達成したいのか」という目的を明確に定義してください。
多くの失敗例は、目的が曖昧なために、手段が目的化してしまうことから生じます。
まず、現状の業務フローの中で最も非効率な「ボトルネック」や、顧客体験を阻害している「ペインポイント」を客観的に洗い出す必要があります。
その上で、「このボトルネックを解消することで、問い合わせ対応時間を30%削減する」といった具体的な数値目標(KPI)を設定してください。
この明確な目的が、後の技術選定、投資判断、効果測定における唯一の判断基準となり、プロジェクトの方向性がブレることを防いでくれます。
小さく試して成果を見える化する
中小企業がDXを進める上での合理的な戦略は、「小さく始めて、すぐに成果を出す」ことです。
全社的な大規模投資ではなく、パイロット導入(スモールスタート)を通じて、早期に成功体験を積み重ねることが不可欠です。
まず、リスクが少なく、効果測定がしやすい特定業務に絞り込み、デジタルツールや新しいプロセスを導入して試行します。
この試行段階で、「このDXによって、実際に〇〇という成果が出た」という具体的な効果を数値で見える化することが極めて重要です。
この小さな成功実績が、現場の抵抗感を解消し、次の段階への予算獲得や経営層のコミットメントを継続させるための最も強力な根拠となるからです。
社員教育・コミュニケーションを重視する
デジタル技術を組織に定着させるためには、技術導入以上に「人」への投資が重要になります。
その理由は、どんなに優れたシステムも、使いこなせる人材がいなければ単なる箱になってしまうからです。
まず、新しいツールの使い方だけでなく、「そのツールがなぜ必要なのか」というDXの意義を伝えるための教育を徹底してください。
また、一方的な情報伝達ではなく、現場からのフィードバックを吸い上げ、システムの改善やプロセス修正に活かす双方向のコミュニケーションを重視すべきです。
社員が「自分たちの意見が反映されている」と感じることで、DXへの参加意欲が高まり、組織全体で変革を支える文化が醸成されていきます。
効果測定と改善サイクルを回す
DXを成功で終わらせるためには、プロジェクトの完了後も、継続的な「効果測定」と「改善のサイクル」を回すことが必須となります。
結論として、ビジネス環境は常に変化しており、システムも合わせて進化し続ける必要があるからです。
具体的には、導入後に設定したKPIを定期的にチェックし、目標との乖離を正確に把握します。
もし目標が達成できていない場合は、システムの機能、運用方法、または目標設定自体を見直す「カイゼン」をすぐに実行してください。
このPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)を文化として定着させると、DXは持続的な経営基盤となり、常に競争優位性を保ち続けることができるのです。
【事例に学ぶ】DXが「うまくいく会社」と「うまくいかない会社」の分かれ道

DXの成否を分けるのは、企業の規模や予算の大きさではありません。
変革に対する「姿勢」と「進め方」に大きな違いがあります。失敗する企業は形から入りがちですが、成功する企業は現場の課題解決に焦点を当てるのです。
ここでは、具体的な失敗ケースと成功ケースを対比させながら、その要因を深掘りします。
他社の事例から学ぶことで、自社が陥りやすい罠を回避し、成功への道筋をより具体的にイメージできるようになるはずです。
【失敗ケース】現場を無視した「ITツールの導入」が招いた形骸化
ある企業では、営業効率化のために高機能な顧客管理システム(SFA)を導入しました。
しかし、入力項目が多すぎて現場の負担が増え、結局誰もデータ入力を行わなくなりました。現場の業務フローを無視し、経営層が「管理したいデータ」を優先させた結果です。
このケースの敗因は、目的が「ツールの導入」になってしまい、現場の利便性が考慮されなかった点にあります。
高額なツールも使われなければ無用の長物です。現場がメリットを感じられないシステムは、必ず形骸化するという教訓です。
【成功ケース】「FAX1枚」の削減から始めた、現場主導のデジタル化
一方、ある中小企業では、FAXでの受注業務を廃止することからDXを始めました。
現場の「紙の管理が大変」という声を拾い上げ、クラウド型の受発注システムに切り替えたのです。その結果、ペーパーレス化が進み、受注処理の時間が大幅に短縮されました。
この成功の要因は、身近な「ムダ」に着目し、小さく始めたことです。
現場が効果を実感しやすいため、次の改善へのモチベーションも高まりました。
派手な変革ではなく、確実な課題解決から始めるアプローチが功を奏した事例です。
なぜ「ITが得意な社員」に任せきりにすると失敗するのか?
「若いから」「パソコンに詳しいから」という理由で、特定の社員にDX推進を丸投げするのは危険です。
その社員に業務負荷が集中し、本来の業務がおろそかになるだけでなく、退職リスクも高まります。また、個人のスキルに依存するため、組織的なノウハウが蓄積されません。
DXは経営戦略であり、一社員のスキルだけで完遂できるものではありません。
社内に専門家がいない場合は、外部のプロフェッショナルを「パートナー」として迎え入れるべきです。
戦略的な視点で伴走してくれるパートナーがいれば、社内担当者も安心してプロジェクトを進められます。
よくある質問(FAQ)|DXがうまくいかないと悩む方々の声に回答

Q1. DXにおける「変革」のゴール設定はどうすれば良いですか?
A1. ゴールは「IT導入」ではなく、「ビジネス成果」に焦点を当てて設定することが重要です。
経済産業省の「デジタルガバナンス・コード3.0」によれば、DXのゴール設定においては、「競争優位性をどう確立するか」という視点が不可欠です。
具体的には、「売上〇%向上」「新規顧客層〇〇%拡大」といった、事業の成長に直結する成果目標を掲げてください。
例えば、「RPAを導入する」というIT目標ではなく、「RPA導入により、社員がコア業務に集中できる時間を週〇時間確保する」といった業務と成果を結びつけた目標を設定することで、DXが経営に貢献する意義が明確になります。
Q2. 定性的なDX効果(社員のモチベーション向上など)は、どのように評価すべきですか?
A2. 定性的な効果も「定量化(数値化)」する工夫を行うことで、投資対効果(ROI)の計算に組み込めます。
社員のモチベーションや満足度といった定性的な効果は、そのままでは評価が難しいものです。
しかし、DX導入前後で匿名アンケートを実施し、「業務のしやすさ」や「会社への満足度」を数値で比較することは可能です。
さらに、「社員満足度の向上」を「離職率の低下」という形で結びつければ、「採用・教育コストの削減」という定量的な利益としてROI計算に組み込めるようになります。
見えにくい効果も、間接的な数値変化を追跡することで評価可能です。
Q3. SaaSと独自のカスタマイズできるシステム開発、どちらを選ぶべきか判断基準を教えてください。
A3. 解決したい課題が「汎用的な効率化」か「競争優位性の確立」かによって判断基準が変わるのです。
SaaSは、会計や人事労務といった標準的で汎用性の高い業務の効率化を図る場合に適しています。
導入が早くコストも抑えられますが、自社の特有の強みや業界独自のプロセスには対応しきれない可能性があります。
一方、カスタマイズできるシステム開発は、競合他社には真似できない独自のノウハウをシステムに組み込み、差別化された競争優位性を確立したい場合に選択すべきです。
Q4. DX推進のリーダーは誰が担うべきでしょうか?
A4. 経営層のコミットメントを示すためにも、最終的なリーダーは「権限を持つ経営層」が担うべきです。
DXは全社的な変革を伴うため、現場やIT担当者だけでは権限不足で壁を乗り越えられません。
DX推進の最終的な責任者は、予算の決定権と組織の慣習を変える権限を持つオーナーや共同創業者などの経営層が担うべきです。
ただし、実務の推進については、現場の業務に精通した「プロジェクトマネージャー」や「推進担当者」を任命し、経営層と現場の橋渡し役を担わせる体制が理想的です。
Q5. 古い既存システム(レガシーシステム)は、どう扱えば良いですか?
A5. 古いシステムの現状を客観的に評価し、「刷新」「延命」「廃棄」の戦略を優先順位をつけて決める必要があります。
古いシステムが残っていると、DXで目指すデータ統合や新しい技術との連携が阻害される大きな原因になります。
まず、そのシステムが「ビジネスの根幹を担っているか」「セキュリティリスクはどうか」を評価してください。
その上で、「データだけを新しいシステムに移す(マイグレーション)」、「段階的に新しい機能へ置き換えていく(モダナイゼーション)」、あるいは「不要なものは廃止する」といった戦略的な判断を下します。
古いシステムを放置することは、将来的なコストとリスクを増大させる可能性もあります。
Q6. プロジェクト途中で予算超過やスケジュール遅延が発生したらどう対応すべきですか?
A6. 発生リスクを認識した上で、関係者との透明性の高いコミュニケーションと「スコープの再調整」を行うべきです。
システム開発やDXプロジェクトにおいて、予算超過や遅延は珍しくありません。
重要なのは、問題発生を隠さず、すぐに経営層と外部パートナーに報告し、原因を明確にすることです。
その上で、最初に定義した「絶対に必要な機能(Must)」に立ち返り、「あれば良い機能(Want)」の導入時期を遅らせるなど、プロジェクトの範囲(スコープ)を調整する合理的な意思決定を行う必要があります。
予期せぬリスクに対応する「変更管理プロセス」を事前に定めておくことが失敗を防ぎます。
Q7. 社内のデジタルリテラシー向上ためには、どのような教育が必要ですか?
A7. 単なるツールの操作方法だけでなく、「データ駆動型思考」を養うための教育が不可欠です。
DXに必要なのは、特定の技術操作スキルだけでなく、「データから課題を発見し、解決策を考える能力」になります。
したがって、教育も、新しいツールの操作マニュアルの伝達だけでなく、「なぜこのデータが必要なのか」「このデータを使ってビジネスをどう改善できるのか」といった、データリテラシーや問題解決の思考プロセスを学ぶ研修に重点を置くべきです。
外部の専門家によるワークショップなどを活用し、経営層から現場まで段階的にレベルアップを図るのが効果的です。
Q8. DXで生まれたデータやシステムの権利は誰に帰属するのでしょうか?
A8. 著作権やデータ所有権については、契約書の中で「誰に帰属するか」を明確に定めることが必須です。
DXによって生まれた新しい顧客データや、外部パートナーが開発したシステムのソースコードの権利は、将来のビジネス展開やトラブルを避けるために極めて重要です。
一般的には、システム開発費用を支払うと、システムの著作権が発注者側(貴社)に帰属することが多いですが、契約形態によって異なります。
特に、システムの根幹となるデータ(情報そのもの)の所有権については、トラブルを防ぐためにも、プロジェクト開始前の契約段階で明確に確認し、書面で取り交わすことが不可欠です。
まとめ|DXはうまくいかない悩みは理由の理解から
本記事では、「DXがうまくいかない」という中小企業の皆様の悩みに寄り添い、変革を阻む「導入の壁」、プロジェクトを失敗に導く「4つの理由」、そして成功へと導くための「5つの具体的なポイント」を解説しました。
改めて、重要なポイントを振り返ります。
DXがうまくいかない正体
- 経営層の理解不足と優先度の低さ
- 社内のIT人材不足やスキルギャップ
- 既存業務文化や抵抗による変化の停滞
- データやシステムの統合が進まない
DX導入が失敗する理由
- 目的や効果が不明確なまま進める
- 技術導入だけに偏り、業務改善が伴わない
- パイロット導入を行わず全社一斉に進める
- 効果測定や改善プロセスが欠けている
DX導入を成功させるポイント
- 経営層から現場までの共通理解を作る
- 解決すべき課題と目的を明確にする
- 小さく試して成果を見える化する
- 社員教育・コミュニケーションを重視する
- 効果測定と改善サイクルを回す
DXを成功させる核となるのは、単なるデジタル技術の導入ではなく、「ビジネスの変革」という明確な目的です。
重要ポイントを押さえることで、課題解決と競争優位の確立に向けたDXの導入を成功させられるでしょう。
失敗の原因と対策を理解した後は、いよいよ実践への一歩です。
「では、具体的に何から着手し、どのような手順で進めれば良いのか」とお考えの方は、こちらの記事でDX導入の具体的な7つのステップを解説していますので、ぜひご覧ください。
関連記事:DX推進は何から始めるべき?成功する進め方の手順を分かりやすく解説 – ビュルガーコンサルティング株式会社
お問い合わせフォームでは「DX開発パートナーズ」をお選びください
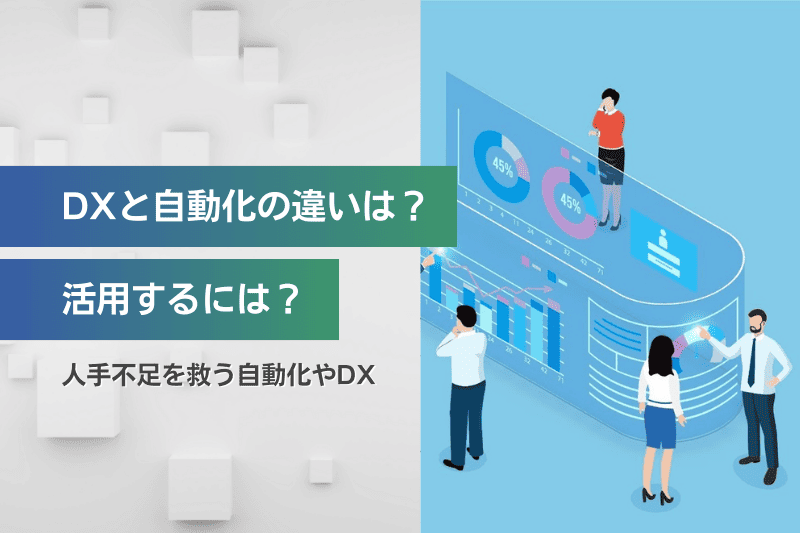
DXと自動化の違いは?中小企業の人手不足を救う成功の秘訣
「DXと自動化って、どう違うの?」と疑問に思っている経営者は少なくありません。
人手不足が深刻化する中、業務効率化の手段として「DX」や「自動化」という言葉をよく耳にするようになりました。
しかし、両者の違いを正しく理解せずに取り組むと、期待した成果が得られない可能性があるのです。
本記事では、DXと自動化の決定的な違いを明確にし、中小企業が人手不足を解消しながら成長するための具体的な方法を解説します。
さらに、現場の抵抗を最小化する導入のコツや、部門別の成功パターンもご紹介します。
この記事を読めば、自社に本当に必要なのはDXか自動化かが判断でき、効果的な施策を選択できるようになるでしょう。
記事監修者

DX開発パートナーは、20年以上の実績を持つリーダーを中心に、
多様なバックグラウンドを持つ若手コンサルタント、PM、エンジニアが連携するチームです。
柔軟で先進的な発想をもとに、DXの課題発見からシステム開発・運用までを一貫して支援しています。クライアントの「DX・システム開発」に関する課題やお悩みをもとに、役立つ情報を発信しています。
混同注意!「DX」と「自動化」の決定的な違いと本来の目的とは?

DXと自動化は似ているようで、実は全く異なる概念です。
多くの企業が「自動化ツールを導入すればDXになる」と誤解していますが、自動化はDXを実現するための手段の一つに過ぎません。
両者の違いを正しく理解することが、投資を無駄にしないための第一歩となります。
ここでは、DXと自動化の本質的な違いと、それぞれの目的を解説します。
単なる「自動化」は作業の効率化、「DX」はビジネスの変革
自動化とは、既存の業務プロセスをデジタル技術で効率化することを指します。
例えば、手作業で行っていた請求書の発行をシステムで自動化したり、Excelでの集計作業をRPAで自動化したりする取り組みが該当します。
自動化の目的は「同じ業務をより速く、より正確に処理すること」であり、業務のやり方そのものは変わりません。
一方、DXは「Digital Transformation(デジタル変革)」の略で、デジタル技術を活用してビジネスモデルや顧客体験そのものを変革することを意味します。
自動化が「現状の業務を楽にする」ものであるのに対し、DXは「ビジネスのあり方自体を変える」ものです。両者の違いを理解せずに取り組むと、投資対効果を最大化できません。
なぜ「自動化」だけで終わると中小企業は成長できないのか?
自動化による効率化は重要ですが、それだけでは競争力の向上にはつながりません。
自動化は既存の業務フローを前提としているため、業務プロセス自体に無駄があれば、無駄を高速で処理しているに過ぎない状態になります。
また、競合他社も同じ自動化ツールを導入すれば、差別化要因にはならないでしょう。
中小企業が成長するには、自動化で得た時間やリソースを、新しい価値創出に振り向ける必要があります。
例えば、自動化で削減した工数を使って顧客との対話時間を増やしたり、新サービスの開発に充てたりすることが重要です。
自動化はコスト削減に貢献しますが、成長の原動力にはなりません。
DXという視点で「顧客にどんな新しい価値を提供できるか」を考えることで、初めて持続的な成長が可能になります。
自動化を「DX(変革)」の土台として活用するための視点
自動化とDXは対立する概念ではなく、自動化はDXを実現するための重要な土台となります。
効率化によって生まれた余裕を、どのように戦略的な取り組みに振り向けるかが鍵です。
自動化で業務時間を削減したら、その時間を顧客満足度向上や新規事業の検討に使いましょう。
具体的には、自動化導入時、削減した工数をどこに再配分するかを事前に計画することが重要です。
計画がなければ、余った時間が別の雑務に消費され、結局は生産性が上がらない状態に陥ります。
自動化を「単なる効率化」で終わらせず、「変革の土台」として位置づけることで、投資対効果を最大化できます。
事例で比較:請求書発行の自動化 vs 顧客体験を変えるDX
請求書発行を例に、自動化とDXの違いを具体的に見てみましょう。
自動化の例: 会計ソフトを導入し、手作業で行っていた請求書の作成と送付を自動化します。
そのため、月末の請求業務にかかる時間が10時間から2時間に削減されました。業務は効率化されましたが、顧客との関係性や提供価値は変わっていません。
DXの例: 請求書の自動化に加えて、顧客ポータルを構築し、顧客が自分で利用履歴や請求明細をいつでも確認できる仕組みを作ります。
さらに、データ分析により顧客ごとの利用パターンを把握し、最適なタイミングでアップセル提案を自動配信する仕組みも導入しました。
前者は業務効率化、後者は顧客体験の変革です。DXでは、効率化を超えて「顧客にとっての価値」を再定義し、競争優位性を構築しています。
自社の取り組みがどちらのレベルにあるかを見極めることが、成功への第一歩となるでしょう。
| 比較項目 | 自動化 | DX |
| 本質 | 既存業務の効率化 | ビジネスモデル・顧客体験の変革 |
| 目的 | 作業を速く・正確にする(現状を楽にする) | 新しい価値を創出する(競争優位性を確立する) |
| 変化の範囲 | 手段が変わるだけ | ビジネスのあり方そのものが変わる |
| 競争力 | コスト削減にはなるが、差別化要因にはなりにくい | 持続的な成長と他社との差別化につながる |
| 相互関係 | DXを実現するための土台・手段 | 自動化で生んだ余力を活かす目的 |
| 具体例(請求書業務) | 会計ソフト導入で作成・送付を自動化→ 社内の工数削減がゴール | ポータル構築やデータ分析で提案を行う→ 顧客体験の向上がゴール |
中小企業の死活問題?今すぐDX・自動化が必要な3つの外的要因

DXや自動化は「いずれやればいい」という悠長な話ではありません。
中小企業を取り巻く環境は急速に変化しており、対応が遅れれば企業の存続そのものが危うくなります。
ここでは、今すぐDXや自動化に取り組むべき3つの外的要因を解説します。
- 採用難・人手不足を補う「デジタル労働力」の確保
- 属人化の解消:ベテラン社員の退職による技術流出を防ぐ
- 残業代規制に対応するための生産性向上
また、DXをできるだけ早く導入したいものの、社員がついていけるかを悩んでいる方は、こちらの記事を併せてご覧ください。
関連記事:デジタル化についていけない?【中小企業】倒産を防ぐ原因と対策を解説
採用難・人手不足を補う「デジタル労働力」の確保
日本の労働人口は減少の一途をたどり、中小企業の人材確保はますます困難になっています。優秀な人材を採用できたとしても、大企業への転職や引き抜きのリスクも高まっているでしょう。
RPAやAIといったデジタル技術を「デジタル労働力」として活用することで、人手不足を補完できます。
例えば、定型的なデータ入力作業をRPAに任せれば、従業員は顧客対応や企画業務など、人間にしかできない創造的な仕事に集中できます。デジタル労働力の確保は、持続可能な経営を実現するための必須条件です。
属人化の解消:ベテラン社員の退職による技術流出を防ぐ
特定の社員にしかできない業務が多い「属人化」は、中小企業の大きなリスクです。
ベテラン社員の退職や病気による長期休暇が発生すると、業務が停止してしまう恐れがあります。
特に、暗黙知として蓄積されている業務ノウハウは、後継者への引き継ぎが難しく、技術流出による損失は計り知れません。
DXや自動化を進めることで、属人化していた業務を標準化し、誰でも対応できる状態を作れます。
業務フローをシステムに組み込むことで、ベテラン社員の知見がデジタル資産として組織に残るでしょう。
また、クラウド上でマニュアルや手順書を共有することで、担当者が変わっても業務の質を維持できます。属人化の解消は、事業継続性を高めるうえで不可欠な取り組みです。
残業代規制に対応するための生産性向上
2024年4月から、厚生労働省は建設業や運送業などの時間外労働の上限規制を適用しました。
残業時間の削減が法律で義務づけられる中、同じ業務量を少ない労働時間でこなす必要があります。
人を増やせば人件費が上がり、収益性が悪化してしまうため、生産性向上による対応が求められるでしょう。
DXや自動化により、1人あたりの生産性を高めることで、残業を減らしながら業務量を維持できます。
例えば、会議の議事録作成をAI文字起こしツールで自動化すれば、会議後の作業時間を大幅に削減可能です。
法規制への対応は待ったなしの課題です。生産性向上を実現するDXや自動化は、コンプライアンスを守りながら競争力を維持するための必須施策となります。
現場の抵抗を最小化するDX・自動化導入のコツ

DXや自動化を成功させるうえで最大の障壁は、技術ではなく現場の抵抗です。
どれだけ優れたツールを導入しても、現場が使わなければ効果は出ません。ここでは、現場の抵抗を最小化し、スムーズに導入するための5つのコツを解説します。
- 自動化に適した「ルール化できる単純作業」の洗い出し法
- IT専門家がいなくても使える「ノーコード・SaaS」の選定基準
- 現場の反対勢力を「味方」に変えるコミュニケーションのコツ
- まずは「週1時間の余裕」を作るスモールスタートの推奨
- 費用対効果(ROI)をどう算出し、投資判断を行うべきか
コツを実践することで、導入の成功率が飛躍的に高まるでしょう。
自動化に適した「ルール化できる単純作業」の洗い出し法
自動化を成功させる第一歩は、適切な業務を選定することです。
すべての業務を自動化しようとすると失敗する恐れがあります。自動化に適しているのは「ルール化できる単純作業」、つまり判断が不要で手順が明確な業務です。
例えば、毎月同じフォーマットで作成するレポートや、決まったルールに基づくデータ入力作業などが該当します。
業務を洗い出す際は、まず1週間分の作業内容を記録しましょう。「この作業は毎回同じ手順で行っている」「判断が必要ない単純作業だ」と感じるものをリストアップします。
次に、各作業の「発生頻度」と「所要時間」を記録してください。頻度が高く時間がかかる作業ほど、自動化による効果が大きくなります。
洗い出しの段階で適切な業務を選べば、導入後の満足度が高まるでしょう。
IT専門家がいなくても使える「ノーコード・SaaS」の選定基準
専任のIT担当者がいなくても、プログラミング知識が不要な「ノーコードツール」や、導入が簡単な「SaaS(クラウドサービス)」を検討することができます。
ノーコードツールやクラウドサービスは、マウス操作だけで設定でき、専門知識がなくても使いこなせます。
ノーコード・SaaSを選ぶ際の基準は以下の3点です。
- 第一に、無料トライアル期間があり、実際に試せるかどうか
- 第二に、日本語のサポート体制が充実しているかどうか
- 第三に、既存のツール(会計ソフトやメールシステムなど)との連携が可能か
また、導入事例が豊富で、自社と似た規模や業種の企業が使っているツールを選ぶと、失敗のリスクを減らせます。
現場の反対勢力を「味方」に変えるコミュニケーションのコツ
新しいツールの導入に対して、現場から反対の声が上がることは珍しくありません。
「今のやり方で問題ない」「新しいことを覚えるのは面倒」という声に対して、押しつけで進めると、かえって抵抗が強まります。
重要なのは、反対する人を敵ではなく、改善のヒントをくれる協力者として捉えることです。
まず、導入前に現場の意見を丁寧にヒアリングしましょう。「どんな不安があるか」「どうすれば使いやすくなるか」を率直に聞き、可能な限り反映します。
次に、影響力のある現場のリーダーに早い段階で相談し、味方になってもらうことが効果的です。
さらに、導入の目的を「業務の押しつけ」ではなく「現場の負担を減らすため」と明確に伝えましょう。実際に削減できる時間を具体的に示すことで、前向きに受け入れてもらいやすくなります。
まずは「週1時間の余裕」を作るスモールスタートの推奨
DXや自動化を始める際、いきなり大規模な導入をする必要はありません。最初から完璧を目指すと、コストが膨らみ、失敗時のダメージも大きくなります。
おすすめは「週1時間の余裕を作る」という小さな目標から始めるスモールスタートです。
例えば、毎週行っている定型レポートの作成を自動化するだけでも、担当者は週1時間の余裕が生まれます。
小さな成功体験を積み重ねることで、「自動化は効果がある」という実感が組織に広がり、次の施策への理解が得やすくなるでしょう。
スモールスタートのもう一つのメリットは、失敗してもダメージが小さい点です。うまくいかなければ別の業務で試せばよく、試行錯誤しやすい環境が整います。
週1時間という小さな目標から始め、徐々に範囲を広げていくアプローチが成功の鍵です。
費用対効果(ROI)をどう算出し、投資判断を行うべきか
DXや自動化への投資判断では、費用対効果(ROI)の算出が欠かせません。
ROIは「(利益額÷投資額)×100」で計算されます。利益額は、削減できた工数を金額に換算した値です。
例えば、月20時間の作業を自動化し、担当者の時給が2,000円なら、年間の利益額は「20時間×2,000円×12ヶ月=48万円」となります。
投資額には、ツールの導入費用だけでなく、月額利用料や社員の研修費用も含めてください。
投資額が100万円なら、ROIは「(48万円÷100万円)×100=48%」です。回収期間は「100万円÷48万円=約2.1年」となります。
全社共通の「正解」となる基準はありませんが、目安となる数字は存在します。KPI Depotによれば、IT投資のROIに関していえば、20%を超えれば投資価値があると判断されます。
ただし、定量的な効果だけでなく、従業員満足度の向上や顧客体験の改善といった定性的な効果も考慮することが重要です。
ROIを明確にすることで、自信を持って投資判断ができるでしょう。
部門別に見るDX・自動化の成功パターンと活用事例

DXや自動化は、部門ごとに適した施策が異なります。
バックオフィス、営業・販促、経営という3つの部門別に、具体的な成功パターンと活用事例を紹介します。
事例を参考に、自社でも応用できる施策を見つけてください。部門ごとの特性を理解することで、効果的な導入計画を立てられるでしょう。
【バックオフィス】経理・総務の入力作業を8割削減する
バックオフィス業務は、自動化による効果が最も出やすい領域です。
経理部門では、請求書の発行や仕訳入力、経費精算といった定型作業が多く存在します。
クラウド会計ソフトやRPAで自動化することで、入力作業を削減できるでしょう。
具体例として、クラウド会計ソフトのfreeeやマネーフォワードを導入すれば、銀行口座やクレジットカードと連携し、自動で仕訳が作成されます。
また、OCR機能を使えば、紙の領収書をスキャンするだけで経費精算が完了するでしょう。
総務部門でも、勤怠管理や有給申請をクラウドシステムに移行することで、紙の申請書やExcel管理から解放されます。
削減した時間を使って、経営分析や業務改善といった戦略的な業務に注力できるようになります。
【営業・販促】メルマガ・顧客管理の自動化で休眠客を掘り起こす
営業・販促部門では、顧客管理とコミュニケーションの自動化が効果的です。
CRM(顧客管理システム)やMAツール(マーケティングオートメーション)を活用すれば、顧客の行動履歴に基づいて最適なタイミングで情報を配信できます。
例えば、資料請求から一定期間経過した顧客に自動でフォローメールを送る仕組みを作れば、休眠客の掘り起こしが可能です。
あるBtoB企業では、MAツールを導入し、Webサイトの閲覧履歴に基づいて興味のある顧客を自動抽出しました。
また、営業活動の記録をCRMに集約することで、担当者が変わっても顧客情報が引き継がれ、属人化を防げます。
自動化により、営業担当者は商談や提案といった本来の業務に集中でき、売上向上につながるでしょう。
【経営】数字の「見える化」を自動化し、即断即決できる体制へ
経営層にとって、タイムリーな経営データの把握は意思決定の質を左右します。
従来の月次決算では、数字が出るまでに1ヶ月以上かかることも珍しくありませんでした。
しかし、BIツール(ビジネスインテリジェンスツール)を導入すれば、売上や経費などの経営指標をリアルタイムで可視化できます。
例えば、TableauやPower BIといったBIツールは、会計システムや販売管理システムと連携し、ダッシュボードで数字を自動集計します。
売上の変化にすぐ気づけるため、販促施策の効果測定や軌道修正もスピーディーに行えるようになるでしょう。
よくある質問(FAQ)|DXと自動化の違いと選び方に悩んでいる方々の声に回答

Q1. 自社の取り組みがDXなのか自動化なのか、どう判断すればいいですか?
A1. 判断の基準は「顧客体験や事業モデルが変わっているか」です。
既存の業務プロセスを効率化しているだけであれば自動化、顧客への提供価値や事業の仕組み自体を変革しているならDXと言えます。
例えば、請求書を手作業から自動作成に変えただけなら自動化ですが、顧客ポータルを作って顧客自身が明細を確認できる仕組みにしたならDXです。
自社の取り組みを振り返る際は、「業務が楽になった」だけなのか、「顧客との関係性や提供価値が変わった」のかを問いかけてみましょう。
後者であればDXへの第一歩を踏み出していると言えます。
Q2. DXと自動化、どちらから始めるべきでしょうか?
A2. まずは自動化から始めることをおすすめします。
DXは大きな変革を伴うため、いきなり取り組むと現場の混乱を招きやすく、失敗リスクも高まります。
一方、自動化は既存の業務フローをそのままに効率化できるため、現場の抵抗が少なく、成果も早期に見えやすい特徴があります。
自動化で業務効率化を実現し、生まれた余裕を使ってDXの構想を練るという段階的なアプローチが現実的です。
小さな成功体験を積み重ねることで、組織全体のデジタルリテラシーが向上し、次のステップへ進みやすくなるでしょう。
Q3. 自動化やDXの導入に失敗する企業の共通点は何ですか?
A3. 最も多い失敗パターンは「現場を巻き込まずにトップダウンで進める」ことです。
経営層が良いと思って導入したツールでも、実際に使う現場の声を聞いていなければ、使われないまま放置される結果になります。
また、導入自体が目的化してしまい、「何のために導入するのか」という目的が曖昧なケースもあり、失敗しやすい傾向があります。
成功させるには、導入前に現場の課題をヒアリングし、目的を明確にすることが不可欠です。さらに、導入後も定期的に効果を測定し、改善を続ける姿勢が重要となります。
Q4. 中小企業でもDXは必要ですか?大企業向けの取り組みではないのでしょうか?
A4. むしろ中小企業こそDXが必要です。
大企業は豊富な人材とリソースで人手不足にも対応できますが、中小企業は限られたリソースで競争しなければなりません。
DXによって業務を効率化し、顧客体験を向上させることで、大企業に対抗できる競争力を手に入れられます。
大企業では承認プロセスに時間がかかる施策も、中小企業なら迅速に実行できるでしょう。
組織の小回りの良さを活かせば、DXは中小企業にとって大きな武器になります。
Q5. 自動化ツールを導入したのに、かえって業務が複雑になってしまいました。どうすればいいですか?
A5. ツールが業務に合っていない可能性が高いです。
自動化ツールは業務フローに合わせて選ぶべきですが、逆にツールに業務を無理やり合わせようとすると、かえって手間が増えてしまいます。
また、高機能すぎるツールを選んでしまい、必要のない機能が多すぎて使いこなせないケースもあります。
まずは現在の業務フローを見直し、本当に必要な機能だけを持つシンプルなツールに切り替えることを検討しましょう。
無料トライアルを活用して、実際の業務で試してから本格導入を判断することで、失敗を防げます。
Q6. 自動化やDXへの投資予算が限られています。どの部門から始めるのが効果的ですか?
A6. バックオフィス部門から始めることをおすすめします。
経理や総務といったバックオフィス業務は、定型的な作業が多く、自動化による効果が最も出やすい領域です。
投資額も比較的少額で済み、ROIが高い傾向があります。
例えば、クラウド会計ソフトなら月額数千円から導入でき、工数削減の効果をすぐに実感できるでしょう。
バックオフィスで成功事例を作れば、社内での理解が深まり、次の投資への予算確保もしやすくなります。
小さく始めて成果を積み重ね、徐々に営業や経営部門へ展開していく段階的なアプローチが現実的です。
Q7. 従業員が高齢で、新しいツールを覚えられるか不安です。導入は難しいでしょうか?
A7. 直感的に使えるツールを選べば、年齢に関係なく導入できます。
「高齢だから無理」という思い込みは、実際には当てはまらないケースが多いです。
重要なのは、マニュアルを読まなくても操作できるシンプルなツールを選ぶことです。
例えば、スマートフォンのように直感的な操作ができるツールなら、年齢を問わず使いこなせすことができるでしょう。
また、導入時に丁寧な研修を行い、困ったときにすぐ聞ける体制を整えることも大切です。
社内で「デジタルに詳しい人」を育て、サポート役として配置すれば、従業員の不安を解消できるでしょう。年齢ではなく、ツール選定とサポート体制が成否を分けます。
Q8. 自動化やDXで削減した時間が、結局別の雑務に使われてしまいます。どう対策すればいいですか?
A8. 削減した時間の使い道を事前に計画することが不可欠です。
自動化で生まれた余裕を「何に使うか」を明確にしないと、別の雑務や会議で埋まってしまいます。
導入前に「削減した工数を顧客対応に充てる」「新サービスの企画に使う」といった具体的な計画を立てることが肝要です。
また、定期的に振り返りの場を設け、実際に計画通りに時間が使われているかを確認しましょう。
もし雑務に消費されているなら、業務の優先順位を見直し、本当に必要な業務かを問い直す必要があります。
時間の再配分まで含めて計画することで、自動化の真価を発揮できます。
まとめ|DXと自動化の違いと成功の秘訣
本記事では、混同されがちな「DX」と「自動化」の決定的な違いと、中小企業が人手不足を解消して成長するための秘訣を解説してきました。
単にツールを導入して作業を速くする「自動化」は、あくまでDXを実現するための「手段」に過ぎません。
大切なのは、自動化によって生み出した余裕を、顧客体験の向上や新しいビジネスモデルの構築といった「変革(DX)」へと投資することです。
この視点を持つことで、初めて他社との差別化と持続的な成長が可能になります。
今回のポイントを振り返ると、以下の3点に集約されます。
「自動化」は守り、「DX」は攻めの戦略
- 自動化で既存業務のムダを削り、デジタル労働力を確保する。
- DXでビジネスのあり方そのものを変え、新しい顧客価値を創出する。
現場の抵抗を抑える「スモールスタート」の原則
- いきなり全てを変えようとせず、まずは「週1時間の余裕」を作る単純作業の自動化から着手する。
- ノーコードツールやSaaSを活用し、IT専門家がいなくても運用できる体制を整える。
部門別の最適化から全社的な「見える化」へ
- バックオフィスの入力作業削減、営業の顧客管理自動化など、効果が出やすい場所から成功体験を作る。
- 最終的には経営データをリアルタイムで可視化し、即断即決できる組織へと進化させる。
人手不足や法規制の変化は、中小企業にとって厳しい逆風ですが、デジタル技術を正しく活用すれば、これまでにない成長のチャンスへと変えることができます。
まずは自社のどの業務を「自動化」し、どのような「変革」を目指すのか、小さな一歩から踏み出してみましょう。
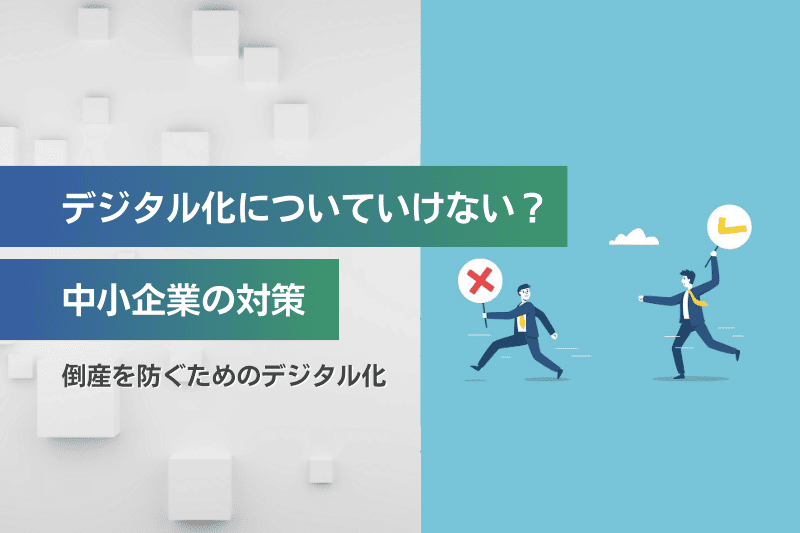
デジタル化についていけない?【中小企業】倒産を防ぐ原因と対策を解説
中小企業の経営者やIT担当者の皆様、日々の業務に追われながら「デジタル化」という言葉にプレッシャーを感じていませんでしょうか。
「周りは進んでいるのに自社は手つかずだ」「どこから手を付ければいいかわからない」という焦りは、多くの企業が抱える共通の悩みです。
しかし、無策のまま放置すれば、時代の変化に取り残されるだけでなく、経営そのものが危うくなるリスクすらあります。本記事では、デジタル化に「ついていけない」と感じる根本原因を解き明かし、中小企業だからこそ実践できる、低コストかつ効果的な対策を解説します。
記事監修者

DX開発パートナーは、20年以上の実績を持つリーダーを中心に、
多様なバックグラウンドを持つ若手コンサルタント、PM、エンジニアが連携するチームです。
柔軟で先進的な発想をもとに、DXの課題発見からシステム開発・運用までを一貫して支援しています。クライアントの「DX・システム開発」に関する課題やお悩みをもとに、役立つ情報を発信しています。
中小企業がデジタル化についていけないと倒産リスクも?今すぐ対応すべき理由

世の中のデジタル化の波は、単なる流行ではなく、企業の生存競争そのものになりつつあります。
多くの経営者が「うちはまだ大丈夫」と考えがちですが、現状維持は後退と同義です。
なぜなら、競合他社がデジタル化によってコストを削減し、顧客サービスを向上させている間に、アナログな手法に固執する企業は相対的に競争力を失っていくからです。
ここでは、なぜ今すぐにデジタル化への対応が必要なのか、切実な理由を掘り下げていきます。
人手不足倒産を防ぐ唯一の手段は「デジタル武装」
日本国内の労働人口が減少の一途をたどる中、中小企業における人手不足は深刻さを増しています。
人を採用しようにも応募が来ない、あるいは採用コストが高騰して手が出ないという状況は、今後さらに悪化すると予測されます。
このような環境下で企業が生き残るためには、限られた人員で従来以上の成果を上げる「生産性の向上」が不可欠です。
実際、中小企業庁が発表した「2024年版中小企業白書」でも、DXの導入目的として「人件費の削減(30.3%)」が上位に挙がっており、人手不足やコスト高への対抗策としてデジタル化が選ばれている現状が浮き彫りになっています。
例えば、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を導入し、データ入力などの単純作業をロボットに任せるとします。
そうすれば、社員は人間にしかできない付加価値の高い業務に集中でき、増員せずとも業務量を維持・拡大できる状態をつくれるのです。デジタル武装は、人手不足による倒産を防ぐための最強の防波堤となります。
また、RPAは何ができるかできないか等、詳しく確認したい方は、こちらの記事を併せてご覧ください。
関連記事:【徹底解説】RPAとは?できること・できないことのまとめ! – ビュルガーコンサルティング株式会社
大企業よりも有利?「小回りの利く組織」こそデジタル化は成功する
「デジタル化は大企業がやるもので、中小企業にはハードルが高い」と思い込んでいませんでしょうか。
実は、意思決定のスピードが速い中小企業こそ、デジタル化の恩恵を最大限に享受できる有利な立場にあります。
大企業では新しいツールを一つ導入するにも、幾重もの承認プロセスや部門間の調整が必要となり、実行までに長い時間を要します。
一方、中小企業であれば、経営者の「やろう」という一声で即座にプロジェクトを始動できるのです。
現場の課題をダイレクトに吸い上げ、小さな改善をスピーディーに繰り返すことが可能です。
実際に、デジタル施策の成果を十分に出せるプロジェクトは全体のおよそ半数弱と言われており、失敗を恐れずに試行錯誤できる環境が重要になります。
小回りの利く組織体制を活かし、まずは特定の業務から小さくデジタル化を始めることが成功への近道です。
完璧なシステムを目指すのではなく、現場の「困った」を即座に解決するスピード感こそが、中小企業の最大の武器になります。
取引先から見放されないために!「インボイス・電子帳簿保存法」への対応
デジタル化への対応を怠ることは、法的なリスクを招くだけでなく、取引先からの信用失墜に直結します。
インボイス制度や電子帳簿保存法といった法改正により、企業間の取引データのデジタル化が急速に進んでいます。
紙の請求書やFAXでのやり取りに固執し続けると、「手間のかかる相手」と見なされるおそれがあります。
例えば、取引先がクラウド上で請求処理を完結させている中、自社だけが郵送で書類を送っていると想像してください。
相手側は自社の書類を処理するためだけに、出社したり手入力したりする手間を強いられます。
このような非効率な取引は、将来的に取引停止の理由になり得ます。また、電子契約を導入すれば印紙代を削減できるといった明確なコストメリットもあります。
法対応を単なる義務と捉えるのではなく、業務フローを見直し、取引先から選ばれ続ける企業になるための好機と捉えるべきです
現場がデジタル化についていけない3つの原因と対策

経営者がいくらデジタル化を叫んでも、現場がついてこなければ改革は絶対に成功しません。
「新しいシステムを入れたのに誰も使わない」「かえって現場が混乱した」という失敗事例は枚挙にいとまがありません。
現場が拒絶反応を示すのには、必ず明確な理由があります。ここでは、現場がデジタル化についていけない主な原因を3つに分類し、それぞれの具体的な対策を提示します。
- ベテラン社員が抱く「心理的ハードル」の正体
- IT担当不在を解消する「相互教育」の仕組み
- 高機能すぎて失敗する「ツール選定」の落とし穴
ベテラン社員が抱く「心理的ハードル」の正体
長年会社を支えてきたベテラン社員ほど、新しいデジタルツールの導入に抵抗感を示す傾向があります。
単なるわがままではなく、「現在のやり方こそが正しい」という強い固定観念や成功体験に基づいている場合が多くみられます。
長年同じ業務を続けていると、その手順が非効率であっても「当たり前」と感じてしまい、疑問を持たなくなるのでしょう。
IPAの「中小規模製造業の製造分野におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)のための事例調査報告書」によれば、日本の生産現場には丁寧さを重んじる素晴らしい風土がある一方で、それがスピードを重視するDXへの心理的な障壁・抵抗勢力になっているという課題も指摘されています。
また、新しいことを覚える手間や、操作を間違えた時の責任に対する不安も大きな要因になります。
ハードルを越えるには、「会社のため」という説明ではなく、「あなた自身が楽になる」というメリットを強調する必要があります。
「この作業が5分で終わるようになる」「面倒な集計作業がなくなる」といった具体的な成功体験を共有し、不安を解消することが重要です。
否定から入るのではなく、現場の不安に寄り添い、丁寧なトレーニングとサポートを提供することで、心理的な壁は徐々に低くなっていきます。
IT担当不在を解消する「相互教育」の仕組み
多くの中小企業では、専任のIT担当者を置く余裕がなく、デジタル化の推進役が不在になりがちです。
特定の詳しい社員に業務が集中してしまうと、その人が退職した瞬間にシステムがブラックボックス化するリスクがあります。
また、通常業務と兼任で改善活動を行わせると、緊急度の高い日常業務に埋もれてしまい、プロジェクトが停滞してしまいます。
問題を解決するには、特定の個人に依存するのではなく、組織全体で教え合う「相互教育」の仕組みを作ることが有効です。
例えば、RPA導入で残業を削減できた部署があれば、その成果と方法を全社で発表し、ノウハウを共有します。
また、改善提案をした社員を正当に評価する制度を設けることで、社員の自発的な参加を促せます。
外部のパートナーを活用する場合でも、丸投げにするのではなく、社内に推進役を立てて共同で進める意識を持つことが、知識の定着につながります。
高機能すぎて失敗する「ツール選定」の落とし穴
「せっかく導入するなら一番いいものを」と考え、多機能で高額なシステムを導入してしまうのは、よくある失敗パターンです。
多くの企業が「完璧な解決策」や「大掛かりなシステム」を最初から求めすぎるあまり、現場の身の丈に合わないツールを選んでしまいがちです。
機能が多すぎるツールは操作が複雑になりやすく、現場の混乱を招くだけでなく、使いこなせない機能のために無駄なコストを払い続けることになります。
ツール選定の際は、現場の課題解決に必要最小限の機能から始めましょう。
また、特定のベンダーの独自仕様に依存しすぎると、将来的な乗り換えが困難になる「ベンダーロックイン」のリスクも考慮しなければなりません。
導入コストだけでなく、運用費や担当者の学習コストも含めたトータルの費用対効果(ROI)を冷静に計算し、本当に必要な投資かどうかを見極める必要があります。
まずはスモールスタートで始め、効果を確認しながら段階的に機能を拡張していくアプローチが確実です。
社員がデジタル化ついていけない状態を防ぐ標準化戦略

デジタル化を成功させるための大前提は、業務の「標準化」です。
誰がやっても同じ結果になるように業務フローが整理されていなければ、どんなに優れたツールを導入しても効果は限定的です。
属人化した業務を整理し、デジタルツールに乗せやすい形に整えることが、現場の混乱を防ぐ鍵となります。
ここでは、社員が無理なくデジタル化に適応できるための標準化戦略について解説します。
- 説明不要!「直感で使えるツール」の選定基準
- 脱・魔改造エクセル!情報のクラウド共有化
- デジタルスキルの「属人化」を防ぐための役割分担
説明不要!「直感で使えるツール」の選定基準
現場に新しいツールを定着させるためには、操作が直感的でわかりやすいものを選ぶことが極めて重要です。
分厚いマニュアルを読まなければ使えないようなシステムは、現場の忙しい社員から敬遠され、すぐに使われなくなってしまいます。「便利さ」が「手間の煩雑さ」を上回る設計こそが、定着化の鍵となるからです。
選定の際は、ITリテラシーが高くない社員でも、画面を見ただけで何をすればいいかがわかるユーザーインターフェース(UI)であるかを確認します。
例えば、ボタンの配置がわかりやすいか、専門用語ではなく日常的な言葉が使われているかといった点です。
また、トライアル期間を活用して実際の現場社員に触ってもらい、「これなら使えそう」という感触を得てから本格導入を決定すべきです。
現場の意見を吸い上げ、彼らが使いやすいツールを選ぶプロセスそのものが、導入後の協力体制を築く第一歩となります。
脱・魔改造エクセル!情報のクラウド共有化
中小企業の現場では、複雑な数式やマクロが組み合わされた「魔改造エクセル」が業務を支えているケースが少なくありません。
しかし、エクセルでの管理は、ファイルが先祖返りしたり、担当者しか修正できなかったりといった「ムダ」の温床になりがちです。
また、ローカル環境に保存されたファイルは、社外からアクセスできず、リモートワークなどの柔軟な働き方を阻害する要因にもなります。
脱エクセルを目指し、情報をクラウド上で一元管理する仕組みへの移行を推奨します。
例えば、稟議書や顧客リストをクラウド型のツールに置き換えるだけで、常に最新の情報を全員が共有できるようになるのです。
検索機能を使えば書類を探す時間が大幅に削減され、情報の透明性も向上します。
最初はエクセルの見た目に近く、データをそのままインポートできるサービスを選ぶと、現場の抵抗感を減らしながらスムーズに移行できます。
情報は「個人の持ち物」ではなく「会社の資産」であるという意識改革を進めましょう。
デジタルスキルの「属人化」を防ぐための役割分担
デジタル化を進める中で、特定の社員だけがツールを使いこなし、他の社員が取り残される事態は避けましょう。
属人化を防ぐには、業務をタスクレベルまで細分化し、誰が何をすべきかを明確にする役割分担が必要です。
業務全体を漠然と捉えるのではなく、「請求書をPDFにしてフォルダに格納する」といった具体的な作業単位に分解して考えます。
タスクを分解することで、「人の判断が必要な業務」と「ルーチンワーク」が明確になるのです。
顧客リストの転記やメール送信といった繰り返し作業は、RPAやマクロを活用して自動化し、機械に任せます。
一方で、顧客への提案や複雑な判断が必要な業務は人間が担当します。このように役割を分担することで、デジタルスキルに自信がない社員でも、自分の担当業務に集中できます。
機械が得意な作業は機械に、人間が得意な作業は人間に。適材適所の配置こそが、組織全体の生産性を最大化するポイントです。
デジタル化についていけないを卒業!中小企業が低コストで始める3ステップ

デジタル化は、巨額の投資をして一気にシステムを入れ替えることだけが正解ではありません。
むしろ、手軽にできる小さな改善を積み重ね、成功体験を肌で感じながら進める方が、リスクも少なく現場の納得感も得やすいです。
ここでは、今日からでも始められる、低コストで確実な効果を生むための3つのステップを紹介します。
- ステップ1:電話・FAX・紙を「1割」減らす試み
- ステップ2:無料ツールで予定共有から始める
- ステップ3:失敗を許容する「1ヶ月の体験期間」
ステップ1:電話・FAX・紙を「1割」減らす試み
いきなり全ての業務をペーパーレス化しようとすると、現場の反発を招き、挫折する可能性が高いです。
まずは「現状の1割」を減らすことを目標に、「なくす」「変える」という視点で業務を見直してみましょう。
業務改善の視点として、ECRS(Eliminate:排除、Combine:結合、Rearrange:入れ替え、Simplify:簡素化)というフレームワークを用います。 まずはこの中のEliminate(排除)を実践し、そもそもその業務が必要なのか、「なくせないか」を最優先で考えます。
例えば、「念のために印刷している会議資料」や「慣用で送っているFAX」など、法的根拠や顧客への付加価値がない作業は廃止の候補です。
過去5年間で一度も使われなかった書類や、なくても困らない確認作業をリストアップし、思い切ってやめてみます。
1割減らすだけでも、用紙代や通信費、そして何より「探す時間」や「管理する手間」という見えないコストが削減されます。
小さな成功体験が、次の改善へのモチベーションにつながります。
ステップ2:無料ツールで予定共有から始める
高価なグループウェアを導入する前に、まずはGoogleカレンダーなどの無料ツールを使って、社内の予定共有から始めてみましょう。
ECRSの「Combine(まとめる)」や「Rearrange(入れ替える)」の実践にもなります。
社員全員のスケジュールが可視化されるだけで、「今、電話しても大丈夫ですか?」という確認の手間や、会議の日程調整にかかる往復メールの時間を大幅に削減できます。
また、無料のチャットツールを導入し、電話や口頭での連絡をテキストに置き換えることも有効です。
言った言わないのトラブルが減り、情報はログとして残るため、後から検索することも容易になります。
無料ツールであれば導入コストはゼロであり、万が一使い勝手が悪くてもすぐに止めることが可能です。
まずは「デジタルでつながる便利さ」を全社員が体感することが、本格的なシステム導入への地ならしとなります。
ステップ3:失敗を許容する「1ヶ月の体験期間」
新しいツールや業務フローを導入する際は、最初から完全定着を目指すのではなく、「1ヶ月のお試し期間」を設けることをお勧めします。
1ヶ月の期間は失敗を許容し、現場からのフィードバックを集めることに集中します。実際に運用してみることで、「ここが使いにくい」「この機能は不要だ」といった具体的な改善点が見えてくるのです。
本段階で重要なのは、短期間でも良いので効果を数値で測定することです。例えば、「作業時間が1日30分から2分に減った」といった定量的なデータを記録します。
もし期待した効果が出なければ、潔く撤退するか、別の方法を試せば良いのです。小さな失敗は経験となり、次の成功への糧となります。
また、成果が出た場合は、ROI(投資対効果)を計算し、本格導入に向けた投資判断の根拠とします。
小さく試して、大きく育てる。サイクルを回すことこそが、デジタル化を成功させる極意です。
よくある質問(FAQ)|デジタル化についていけないと悩んでいる方々の声に回答

Q1. ITに詳しい社員が一人もいません。何から手を付けるべきでしょうか?
A1. まずは「紙・ペン・FAX」を使っている業務を一つだけデジタルに置き換えてください。専門知識は不要です。
例えば、ホワイトボードの予定表をスマートフォンのカレンダーアプリに変えるだけで、外出先から予定を確認できるようになります。
こうした身近な「便利さ」を実感することが、社内のITアレルギーを克服する最短ルートとなります。
Q2. デジタル化の費用対効果(ROI)はどのように計算すれば良いですか?
A2. 「削減された作業時間 × 担当者の時給」をベースに計算します。
例えば、月間20時間のデータ入力作業がシステム化でゼロになった場合、時給2,000円なら月4万円のコスト削減とみなされます。
加えて、ミスによる手戻りの減少や、顧客対応時間の増加といった定性的な効果を積み上げて投資判断の材料にするのです。
Q3. 高価なシステムを導入して、現場が使いこなせなかったらと思うと怖いです。
A3. 1ヶ月程度の「体験期間(トライアル)」があるツールを選び、現場に判断させてください。
経営者が機能だけで選ぶのではなく、実際に使う社員に操作感を試してもらうことが不可欠です。
現場から「これなら今の業務が楽になる」という声が出てから本契約に進むことで、導入後の形骸化(使われなくなること)を防げます。
Q4. ツールを導入する際、セキュリティ対策に多額の費用がかかりますか?
A4. 信頼性の高い「クラウドサービス(SaaS)」を活用すれば、低コストで対策が可能です。
自社で専用サーバーを構築して守るよりも、すでに強固なセキュリティを備えている既存のサービスを利用する方が安価で安全です。
まずは「二段階認証の設定」や「パスワード管理の徹底」といった基本的な運用ルール作りから始めてください。
Q5. 従業員の満足度などの「目に見えない効果」は、どう評価すべきですか?
A5. アンケートによる数値化や、採用コストの削減額として換算します。
例えば、デジタル化で残業が減り離職率が改善すれば、将来的な「採用・教育コストの削減」という大きな利益になります。
導入前後に匿名のアンケートを行い、「業務のしやすさ」を5段階評価で比較することも、立派な効果測定の手法です。
Q6. 既存のExcel管理が複雑すぎて、デジタル化に移行できる気がしません。
A6. 全てを一度に移そうとせず、特定のデータ項目から「情報のクラウド化」を試みてください。
「魔改造エクセル」を一度に廃止するのは困難です。まずは在庫データや顧客リストなど、共有頻度が高い情報からクラウドツールへ移行します。
誰でも最新情報にアクセスできる利便性を共有することで、徐々に脱エクセルの機運を高められます。
Q7. 小さなデジタル化を繰り返すだけで、本当に経営リスクは下がりますか?
A7. はい。小さな効率化の積み重ねが、人手不足への耐性とスピードを生みます。
一つの業務で月5時間の余裕が生まれれば、年間で60時間の創出になるのです。
その時間を「新しいサービスの企画」や「顧客への手厚いフォロー」に充てることで、売上向上につながる好循環が生まれます。デジタル化による真の経営改善です。
Q8. 導入したシステムが数年で使えなくなるリスクはありませんか?
A8. 変化に合わせてアップデートされる「クラウド型」を選ぶことでリスクを軽減できます。
買い切りのシステムと違い、クラウドサービスは法改正や技術トレンドに合わせて自動で機能が更新されるのです。
将来的なインボイス制度や電子帳簿保存法への対応も提供元が行うため、常に最新の状態で使い続けることが可能になります。
まとめ|デジタル化についていけない方には「小さな一歩」から
本記事では、中小企業がデジタル化につまずく原因と、具体的な対策について解説してきました。
デジタル化は決して大企業だけのものではなく、むしろ中小企業が生き残るための強力な武器となります。
ここで、改めて重要なポイントを振り返ります。
- 人手不足の解消:デジタル化は採用難の時代における唯一の解決策であり、生産性向上の鍵です。
- 現場の心理的ハードル:「楽になる」というメリットを提示し、丁寧なサポートで不安を取り除きます。
- 標準化と役割分担:業務をタスクレベルで分解し、直感的なツールを選んで属人化を防ぎます。
- スモールスタート:まずは「なくす」ことから始め、無料ツールや試用期間を活用してリスクを抑えるのです。
「デジタル化についていけない」と悩むのは、決して恥ずかしいことではありません。しかし、何もせずに立ち止まっていることこそが最大のリスクです。
まずは身近な業務の「ムダ」を見つけ、小さな改善から始めてみてはいかがでしょうか。
もし、自社の課題がどこにあるのか明確でない、あるいはどのツールを選べば良いか迷っているという場合は、専門家の知見を借りるのも一つの賢い選択です。
外部パートナーと共に、貴社の業務に最適なデジタル化のロードマップを描くことで、無駄な投資を避け、最短距離で成果にたどり着きます。
また、デジタル化や業務改善アイデアを幾つか調べてから実践を検討したい方は、こちらの記事を併せてご覧ください。
関連記事:業務改善のアイデアが思いつかない!簡単に実施できる業務改善案5選のご紹介 – ビュルガーコンサルティング株式会社
まずは一度、現状の悩みをご相談ください。貴社の未来を変える第一歩を、共に踏み出しましょう。
お問い合わせフォームでは「DX開発パートナーズ」をお選びください





