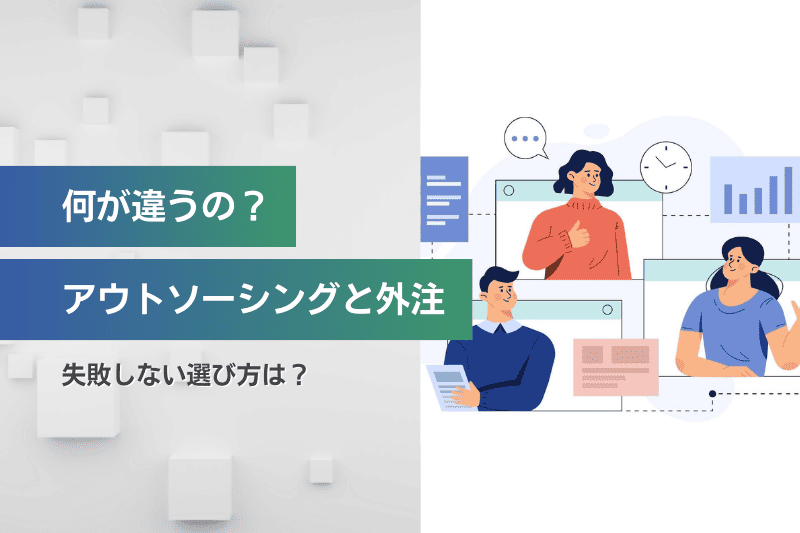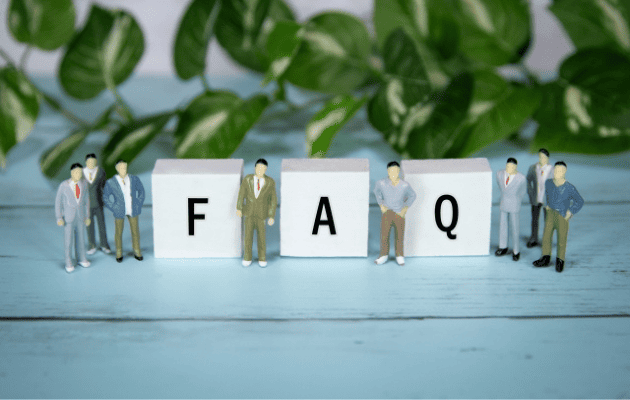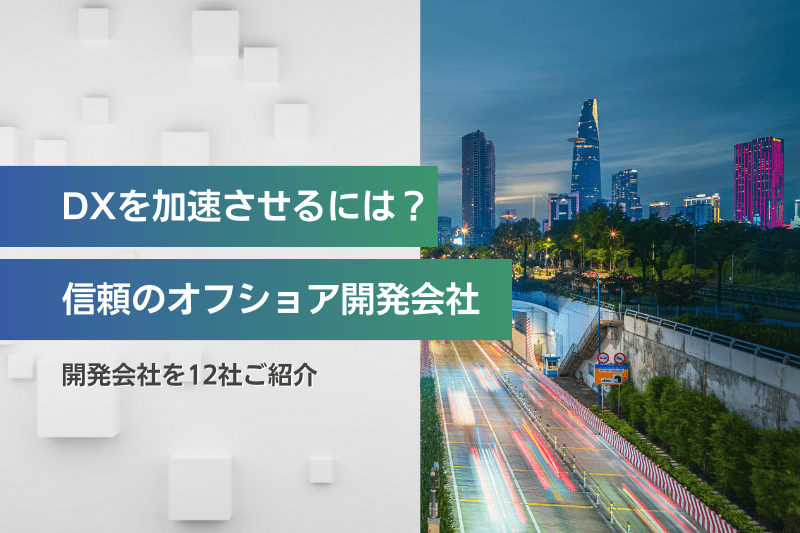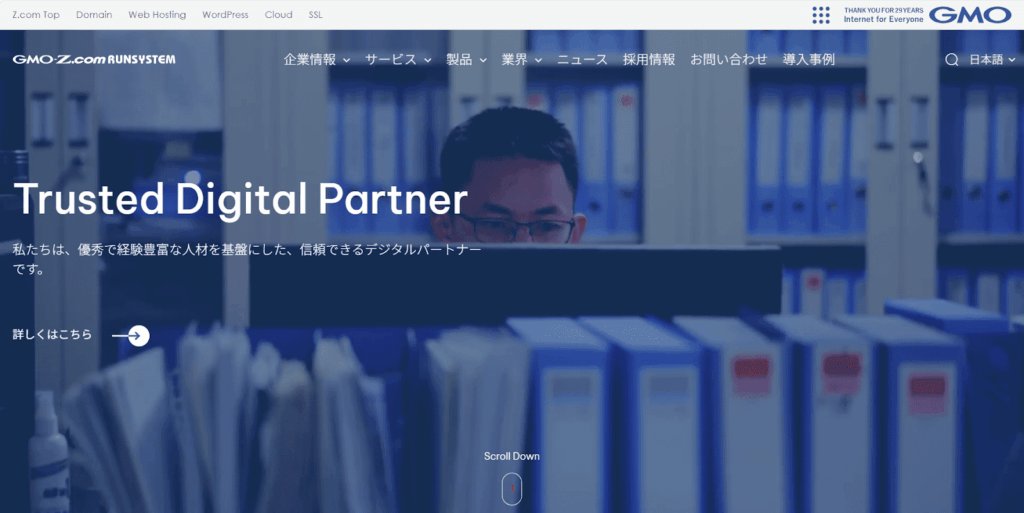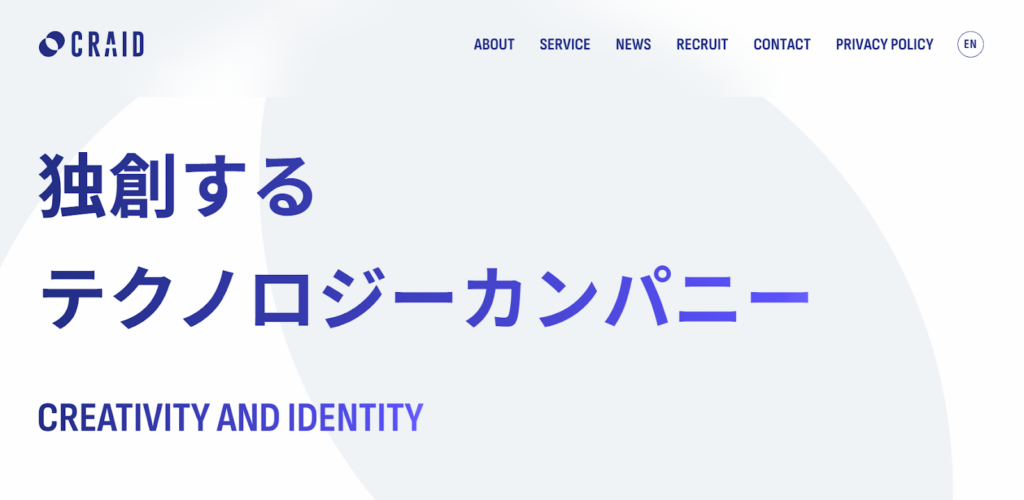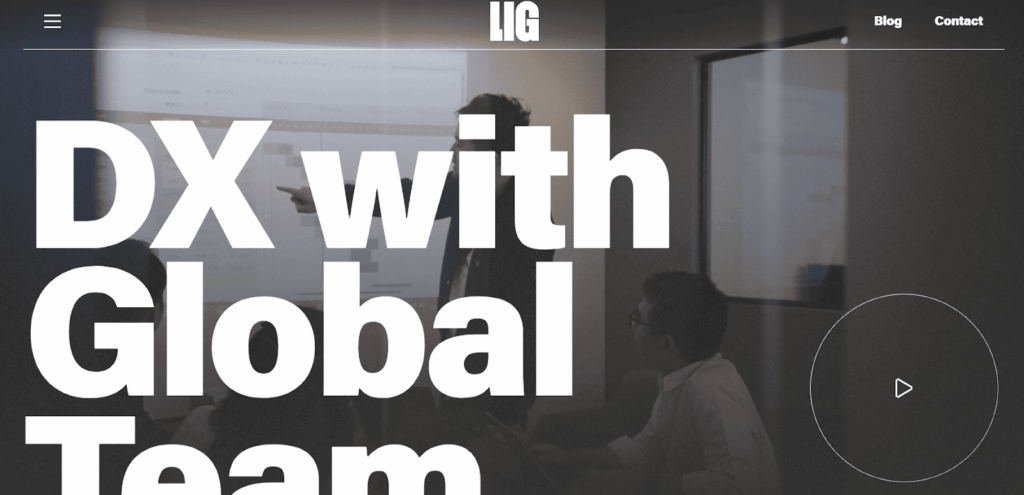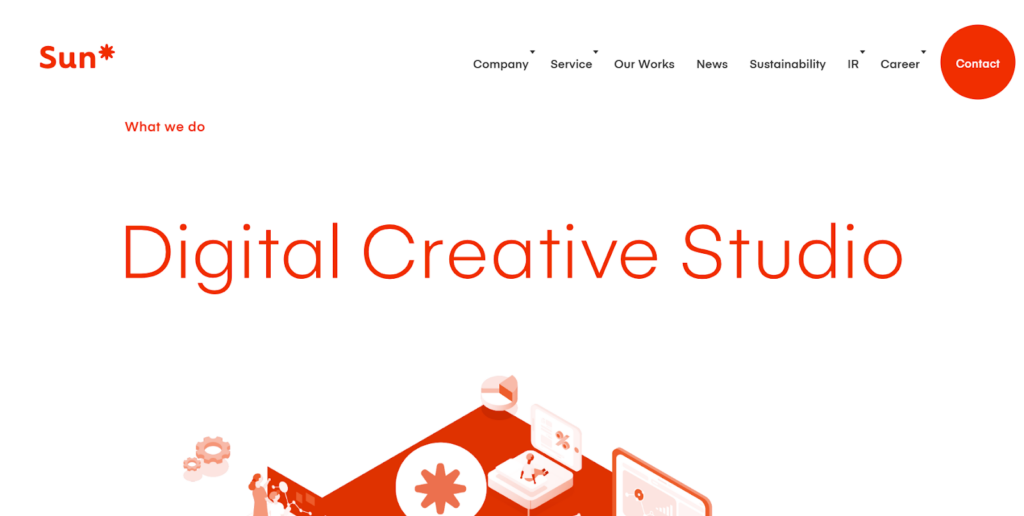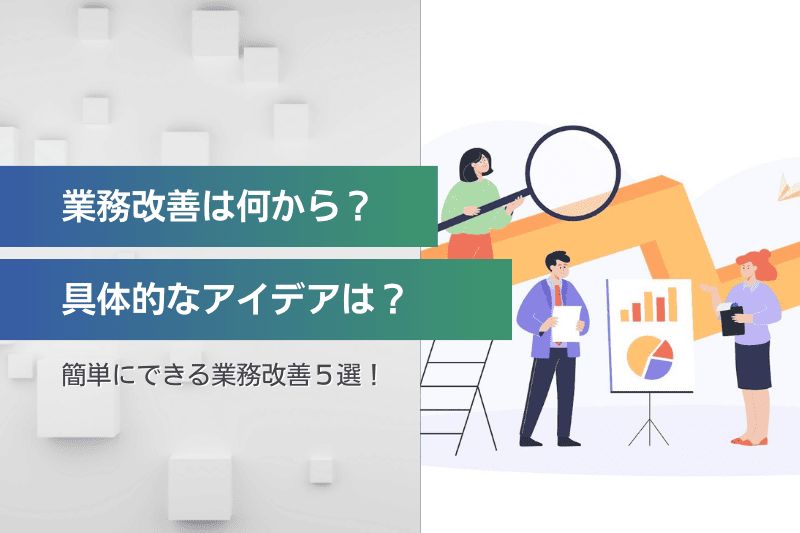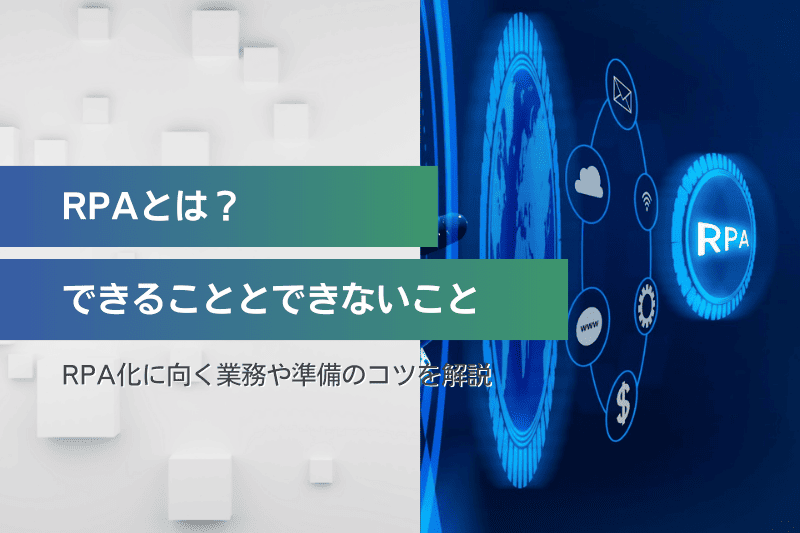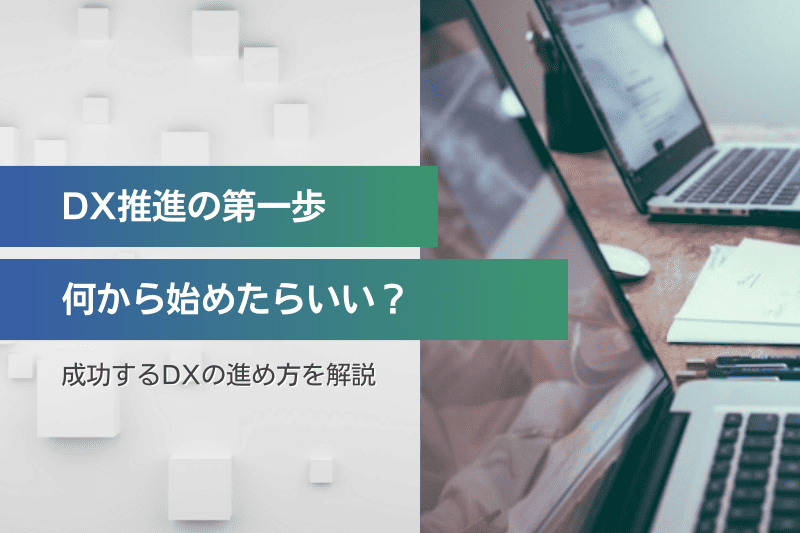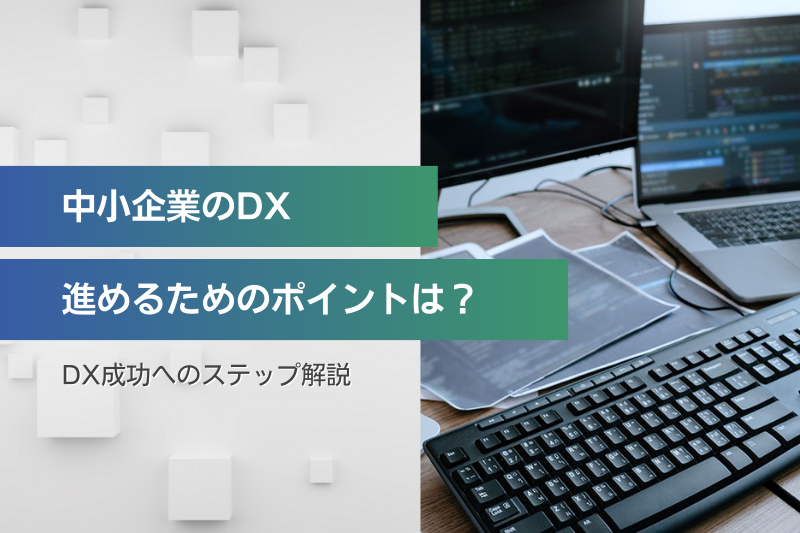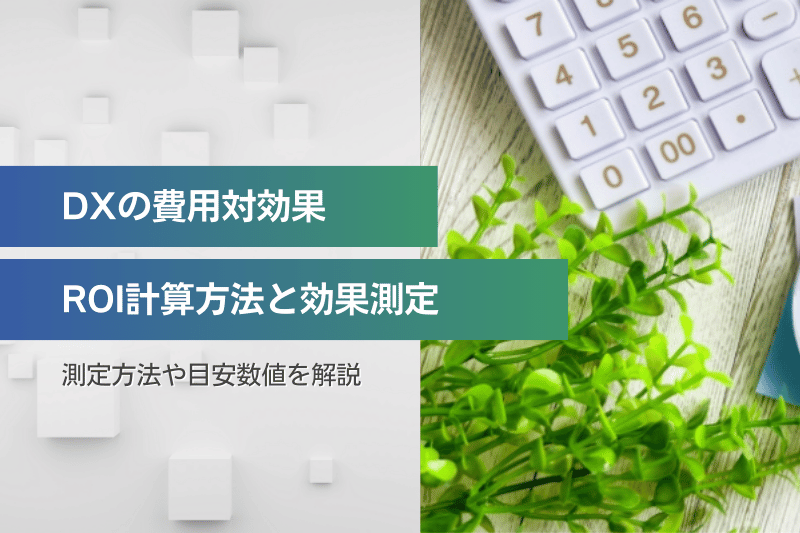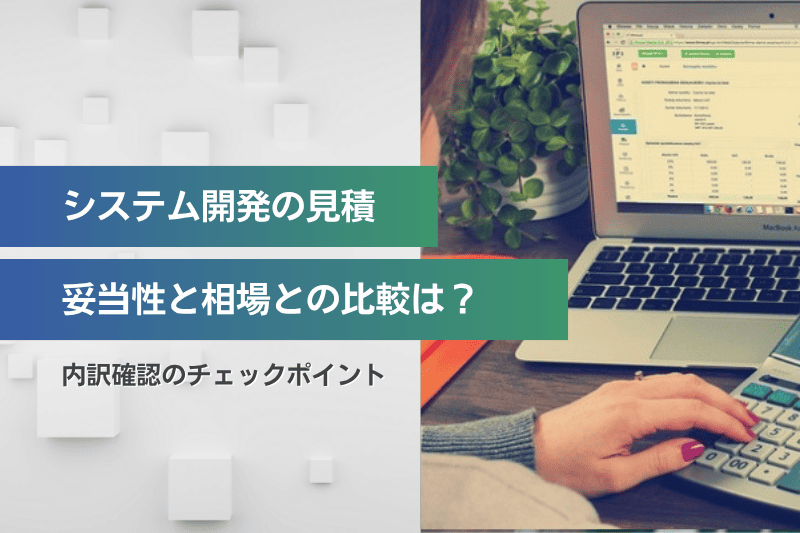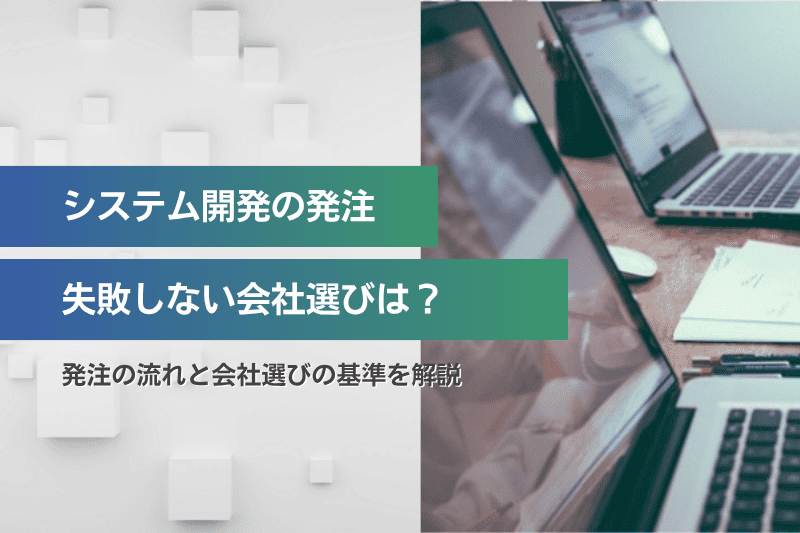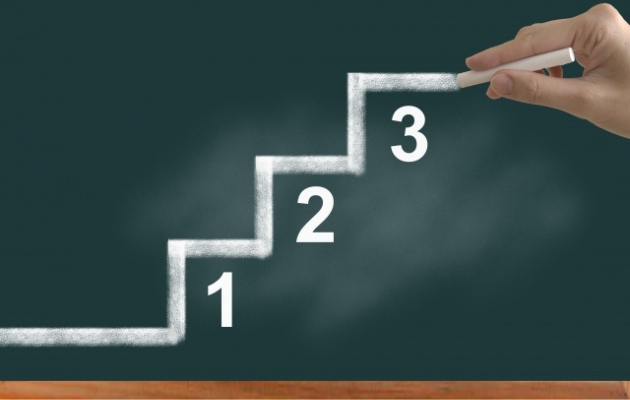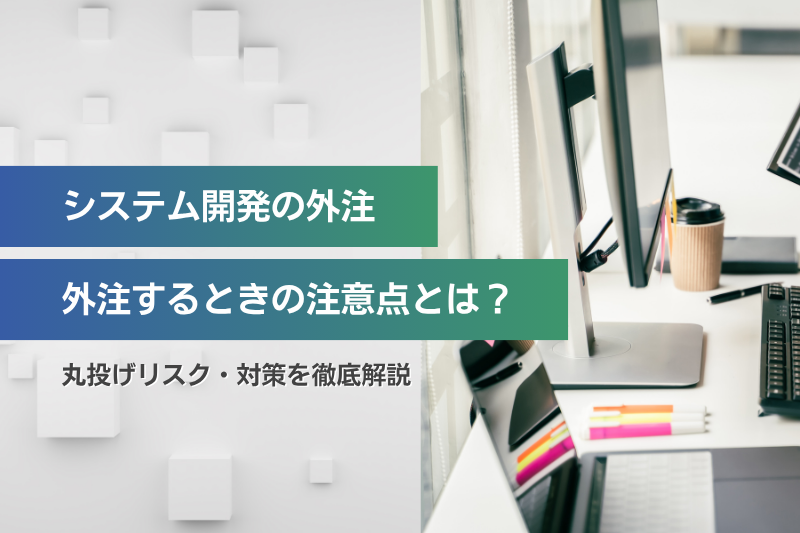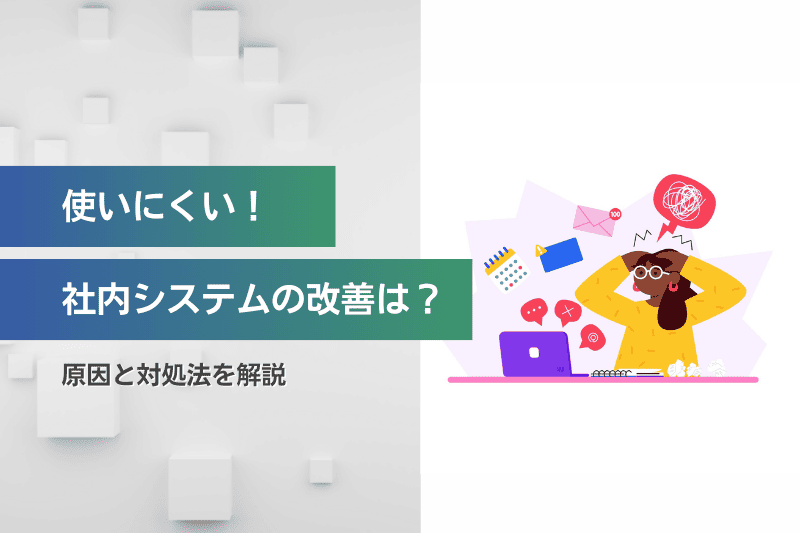
社内システムが使いにくい!原因は?改善の進め方と対処法を解説
今の社内システムに対して「動作が遅くてイライラする」「画面が見づらくて入力ミスが頻発する」といった不満を抱えていませんか。
システムに関する知識がない経営者や担当者にとって、何が原因でシステムが使いにくくなっているのかを特定するのは容易ではありません。
しかし、使いにくいシステムを放置すると、業務効率が下がるだけでなく、従業員の士気低下や重要な経営判断の遅れにつながる恐れがあります。
本記事では、社内システムが使いにくくなる根本的な原因と、リスクを回避して「本当に使えるシステム」を構築するための具体的な手順を解説します。
この記事を読めば、自社の課題をどのような視点で解決し、プロジェクトを進めればよいかが明確になるでしょう。
記事監修者

DX開発パートナーは、20年以上の実績を持つリーダーを中心に、
多様なバックグラウンドを持つ若手コンサルタント、PM、エンジニアが連携するチームです。
柔軟で先進的な発想をもとに、DXの課題発見からシステム開発・運用までを一貫して支援しています。クライアントの「DX・システム開発」に関する課題やお悩みをもとに、役立つ情報を発信しています。
なぜ社内システムは「使いにくい」と感じるのか?

多くの企業がDXを推進する中で、導入したシステムが現場に定着せず、かえって混乱を招くケースが後を絶ちません。
高額な費用をかけて導入したのに、現場からは不満ばかり聞こえてくるという悩みを持つ経営者は非常に多いのが実情です。
なぜ、業務を効率化するためのシステムが、逆に現場の負担になってしまうのでしょうか。
システムが使いにくいと感じる背景には、単なる操作性の良し悪しだけではありません。
経営層と現場、そして開発側の三者間における認識の乖離が大きな要因です。
特に中小企業においては、IT担当者が不在であったり、兼務であったりすることが多く、専門的な視点での設計が不十分になりがちです。
ここでは、システムが「使いにくい」と感じられる背景と、その実態について深掘りしていきます。
現場の生産性を著しく低下させる「使いにくさ」の正体
システムが使いにくいと感じる最大の要因は、ユーザーが期待する操作感と実際の挙動との間に生じる「摩擦」にあります。
例えば、一つの注文データを入力するために何度も画面を切り替える必要がある場合、その手間は小さなストレスとして蓄積されます。
このような操作の摩擦は、単なる「慣れ」の問題ではなく、明確な「時間的コスト」として経営に跳ね返ってくるのが現実です。
システム導入による定量的な効果として「工数削減」が期待されますが、使いにくいシステムは逆に工数を増大させます。
具体的には、直感的に操作できないためマニュアルを何度も確認したり、システムの反応速度が遅く待ち時間が発生したりします。
無駄な時間は、本来であれば顧客対応や商品開発といった「利益を生み出す業務」に充てられるべき貴重なリソースです。
使いにくさの正体とは、従業員の思考と時間を奪い、企業の競争力を削ぐ「見えないコスト」そのものであるといえます。
社内システムが使いにくくなる3つの根本原因

システムが使いにくくなるのには、必ず明確な理由が存在します。
理由は、技術的な問題だけでなく、開発プロセスやコミュニケーションのあり方に起因することがほとんどです。
ここでは、社内システムが使いにくくなってしまう3つの根本的な原因について、専門的な観点から解説します。
- UI/UXデザインの欠如と「開発者目線」の設計
- 業務フローとシステムの「ミスマッチ」
- システムの老朽化と継ぎ足しによる「複雑化」
UI/UXデザインの欠如と「開発者目線」の設計
使いにくいシステムの多くは、実際にシステムを利用するユーザーの視点(UX:ユーザー体験)が欠落したまま設計されています。
開発を担うエンジニアは、機能要件を満たすことを最優先に考える傾向があり、使いやすさは二の次になりがちです。
IPAの「組込みソフトウェア開発における品質向上の勧め[ユーザビリティ編]」によれば、多くの組込みエンジニアが機能実装に注力する一方で利用者視点が置き去りになることから、ユーザビリティ低下を招き得るとの指摘があります。
結果、機能としては正しく動作しても、現場の業務フローに合わない「開発者目線」のシステムが出来上がってしまいます。
品質の良いシステムとは、単にバグがないだけでなく、ユーザーにとって使いやすく、将来の拡張性があることも含まれるのです。
デザインの専門家が関与せず、機能実装だけでプロジェクトを進めてしまうと、現場の実状とかけ離れたシステムが生まれる原因となります。
業務フローとシステムの「ミスマッチ」
システム開発において最も重要なのは、何を作るかではなく業務をどう変えたいかという目的を明確にすることです。
しかし、発注側と開発側のコミュニケーションが不足していると、業務の細部に関する認識のズレが生じます。
発注側が「言わなくても分かるだろう」と考えている業務の常識は、外部の開発者には伝わっていないことがほとんどです。
この認識のズレが解消されないまま開発が進むと、完成したシステムが実際の業務フローと噛み合わない事態が発生します。
業務の実態を深く理解しないままシステム化を進めることは、使いにくいシステムを生み出す大きな要因です。
システムの老朽化と継ぎ足しによる「複雑化」
長年にわたって同じシステムを使い続けている場合、老朽化と度重なる改修(継ぎ足し開発)が使いにくさを招くケースがあります。
ビジネスの変化に合わせて機能を追加することは必要ですが、全体の設計を見直さずに機能だけを追加し続けると、システム内部が複雑化します。
いわゆる「スパゲッティコード」の状態になり、動作が重くなったり、一部の修正が他の機能に悪影響を及ぼしたりするようになるのです。
さらに、経済産業省の「DXレポート」によると、このようなシステムはレガシーシステムと呼び、レガシーシステムの本質は自社システムの中身がブラックボックス化されることを指しています。
システムが複雑になりすぎると、新しい技術やUIを取り入れることが難しくなり、結果として現場は古い使い勝手のまま我慢を強いられます。
さらに、特定のベンダーに依存しすぎる「ベンダーロックイン」の状態になると、改修に多額の費用と時間がかかり、改善が困難な悪循環に陥ってしまうのです。
使いにくい社内システムを放置することで生じるリスク

使いにくいシステムを使い続けることは、単なる不便さにとどまらず、企業経営に深刻なリスクをもたらします。
放置することで発生するデメリットを正しく理解し、早期の対策を検討しましょう。
ここでは、使いにくいシステムが引き起こす具体的な2つのリスクについて解説します。
従業員満足度の低下と「シャドーIT」の蔓延
使いにくいシステムは、従業員にとって日々のストレス源となり、仕事へのモチベーション(従業員満足度)を低下させます。
DXの成果として、従業員満足度の向上や離職率の低下といった定性効果も重要な評価指標となります。
システムが使いにくいと、従業員は「会社は現場のことを分かっていない」と感じ、組織への信頼を失うきっかけになりかねません。
さらに深刻なのが、会社が許可していない無料ツールを勝手に使い始める「シャドーIT」の蔓延です。
正規のシステムが使いにくいと、現場は業務を遂行するために、個人のクラウドストレージやチャットツールを使い始めます。
結果、情報漏洩のリスクが飛躍的に高まり、企業の社会的信用を一瞬で失墜させる可能性を秘めているのです。
ヒューマンエラーの増加とデータの信頼性欠如
UIが分かりにくいシステムや、操作手順が複雑なシステムは、入力ミスや操作ミスといったヒューマンエラーを誘発します。
例えば、似たようなボタンが隣接していたり、必須項目の表示が曖昧だったりすると、誤ったデータが登録される確率が高まります。
入力ミスによる手戻りの修正作業には多くの時間がかかり、年間で見ると相当な損失になることも珍しくありません。
また、システム内のデータに誤りが増えると、経営判断に必要なデータの信頼性が失われます。
DXの目的はデータを活用してビジネスを変革しようと、データ自体の精度が低ければ、正しい意思決定を行うことは不可能です。
不正確なデータに基づいた経営は、誤った投資や在庫管理を招き、大きな損失を出すリスクがあります。
失敗しない「使いやすい社内システム」構築の進め方
では、現場が満足し、経営にも貢献する使いやすいシステムを構築するにはどうすればよいのでしょうか。
システム開発を成功させるためには、外部に丸投げするのではなく、発注者が主体的にプロジェクトに関わることが不可欠です。

ここでは、失敗しないための具体的な進め方を3つのステップで解説します。
- 現場ユーザーを巻き込んだ「要件定義」の徹底
- デザイン思考を取り入れたUI/UX設計のプロセス
- 導入後の「利用定着化(デジタルアダプション)」支援
現場ユーザーを巻き込んだ「要件定義」の徹底
使いやすいシステムを作るための第一歩は、実際にシステムを利用する現場ユーザーを巻き込んで要件定義を行うことです。
経営層やシステム担当者だけで仕様を決めてしまうと、現場の実態と乖離したシステムになりがちです。
まずは現場の担当者にヒアリングを行い、現在の業務フローにおける課題やボトルネックを数値で把握します。
具体的には月間の入力工数を何時間削減するといった、具体的な数値目標(KPI)を設定します。
この目標設定の段階で現場の声を取り入れることで、本当に必要な機能と優先順位が明確になるのです。
現場の意見を聞くことは、導入後の「自分たちのシステムだ」という当事者意識(オーナーシップ)の醸成にもつながります。
デザイン思考を取り入れたUI/UX設計のプロセス
要件が固まったら、次はどのように画面や操作に落とし込むかを設計します。
この段階では、プロトタイプ(試作品)を作成して検証する「デザイン思考」のプロセスが重要です。
いきなり完成品を作るのではなく、画面のイメージ図を現場のユーザーに触ってもらい、フィードバックを早期に得るようにします。
ボタンの配置はここで使いやすいかといった確認を繰り返すことで、開発後の大きな手戻りリスクを最小限に抑えられます。
また、単に言われた通りに作るだけでなく、ビジネスの課題を理解して提案してくれる伴走型のパートナーを選定することが大切です。
導入後の「利用定着化(デジタルアダプション)」支援
システムは完成して終わりではなく、現場で使われて初めて価値を生み出します。
新しいシステムに慣れるまでには時間がかかるため、開発段階から導入後の教育やサポート体制を計画に含めておかなければなりません。
導入コストを計算する際は、システム構築費だけでなく、社員研修の人件費といった「隠れコスト」も考慮すべきです。
開発会社との契約においても、リリース後の保守・運用サポートが含まれているかを確認します。
使い方が分からない時にすぐに質問できる体制や、現場の要望に応じて細かな改善を継続できる体制が定着率を左右させるのです。
システムが定着し、業務が標準化されれば、属人化が解消され、長期的な生産性の向上につながります。
よくある質問(FAQ)|社内システムが使いにくいと感じた方々の声に回答

Q1. システムの「使いにくさ」を具体的に数値化する方法はありますか?
A1. 現場の作業時間を「改善前」と「改善後」で比較し、人件費換算することをお勧めします。
例えば、特定の入力作業に1名あたり毎日30分かかっている場合、月間(20日)で10時間のコストが発生しています。
従業員100名の企業であれば、月間1,000時間が「使いにくいシステム」によって失われている計算になるのです。
経済産業省のDXレポートによると、レガシーシステムによる経済損失が指摘されており、この時間を人件費に換算することで、改善に向けた合理的な投資判断が可能になります。
Q2. UI(デザイン)を改善するだけで、本当に生産性は上がるのでしょうか?
A2. はい、劇的に向上する可能性があります。
使いやすいUIは、ユーザーの「認知負荷(情報を理解するための脳の負担)」を軽減させるのです。
デザインの改善は単なる「見た目の変更」ではなく、業務フローの最適化そのものであると捉えてください。
Q3. 開発会社に「伴走型」で依頼すると、費用がかなり高くなるのではありませんか?
A3. 短期的には高額に見えますが、長期的な「トータルコスト」は抑えられる傾向があります。
安価な「言われた通りに作るだけ」の会社に依頼すると、導入後に使い勝手が悪く、大規模な改修が必要になるリスクが高まるでしょう。
最初からビジネス課題を理解するパートナーと組むことで、手戻り(作り直し)のコストを最小限に抑えられ、最終的な費用対効果(ROI)は高くなります。
Q4. 現場から「新しいシステムは覚えるのが面倒」と反対されないか心配です。
A4. 開発の初期段階から現場のキーマンをプロジェクトに巻き込むことが最も有効な対策です。
「会社から押し付けられたツール」ではなく「自分たちの意見が反映されたツール」と認識してもらうことが重要です。
要件定義の段階でヒアリングを行い、プロトタイプ(試作品)を触ってもらうプロセスを経ることで、導入時の心理的ハードルを下げ、スムーズな定着(デジタルアダプション)を促せます。
Q5. 既存システムが古すぎて、何から手をつければいいか分かりません。
A5. まずは、現在のシステムが業務のどの部分で「ボトルネック(障害)」になっているかを可視化しましょう。
すべての機能を一度に刷新するのはコストもリスクも高いため、最も現場の負担が大きい機能から段階的に改修する手法(マイクロサービス化など)も検討できます。
専門家に現状のシステム診断を依頼し、リスクと優先順位を明確にすることから始めるのが合理的です。
Q6. 中小企業でも、大手のようなデザイン思考を取り入れた開発は可能ですか?
A6. もちろんです。むしろ意思決定の早い中小企業こそ、相性が良い手法です。
デザイン思考とは、巨額の予算をかけることではなく「徹底的にユーザー視点に立つ」という姿勢を指します。
短期間で試作と検証を繰り返すアジャイル型の開発スタイルを採用しているパートナーを選べば、限られた予算の中でも「本当に現場が求める使い勝手」を追求できます。
Q7. 開発パートナーを選ぶ際、何を基準に「信頼性」を判断すべきですか?
A7. 過去の制作実績だけでなく、「自社の業界や業務フローに対する理解度」を重視してください。
単にIT技術に詳しいだけでなく、経営課題や現場の悩みに寄り添った提案をしてくれるかを確認します。
メリットだけでなく、あえてデメリットやリスクを提示してくれる会社は、誠実で根拠のある提案をしている可能性が高いです。
また、導入後のサポート体制が具体的に示されているかも重要なチェックポイントになります。
Q8. システムを改善した後、その効果をどうやって測定すればよいですか?
A8. 導入前に設定したKPI(重要業績評価指標)の達成度を確認してください。
例えば「月間の残業時間の削減数」や「入力ミスによる手戻り件数の減少率」など、具体的な数値で比較します。
また、定性的な効果として社内アンケートによる満足度の変化を測定することも有効です。
まとめ|「使いにくいシステム」から企業のDXを加速させる「使いやすいシステム」へ
本記事では、社内システムが使いにくい原因と改善の進め方について解説しました。
社内システムが使いにくくなる3つの根本原因
- UI/UXデザインの欠如と「開発者目線」の設計
- 業務フローとシステムの「ミスマッチ」
- システムの老朽化と継ぎ足しによる「複雑化」
失敗しない「使いやすい社内システム」構築の進め方
- 現場ユーザーを巻き込んだ「要件定義」の徹底
- デザイン思考を取り入れたUI/UX設計のプロセス
- 導入後の「利用定着化(デジタルアダプション)」支援
システムの課題を放置することは、生産性の低下だけでなく、セキュリティリスクや経営判断の遅れといった深刻な事態を招きます。
自社だけで解決することが難しい場合は、専門家の知見を借り、合理的な根拠を持ってプロジェクトを進める形をお勧めします。
さらに、使いやすい社内システムの外注のリスクや対策について詳しく知りたい方は、こちらの記事を併せてご覧ください。
関連記事:
システム開発を外注に丸投げするのは危険?リスクと対策を徹底解説 – ビュルガーコンサルティング株式会社
まずは現在のシステム利用状況に関する社内アンケートを実施し、現場のリアルな声を知ることから始めてみてはいかがでしょうか。
正しい決断を下すために、メリットとデメリットの両方を提示してくれるプロに相談し、納得のいく改善を進めてください。
お問い合わせフォームでは「DX開発パートナーズ」をお選びください