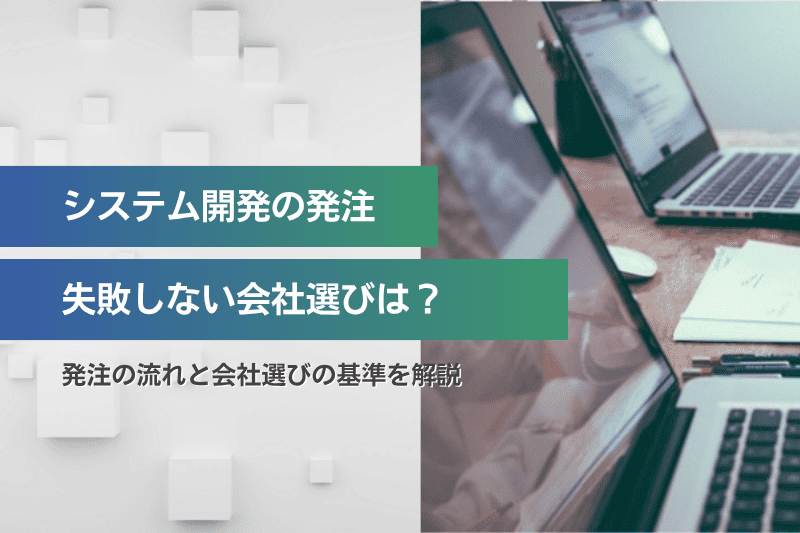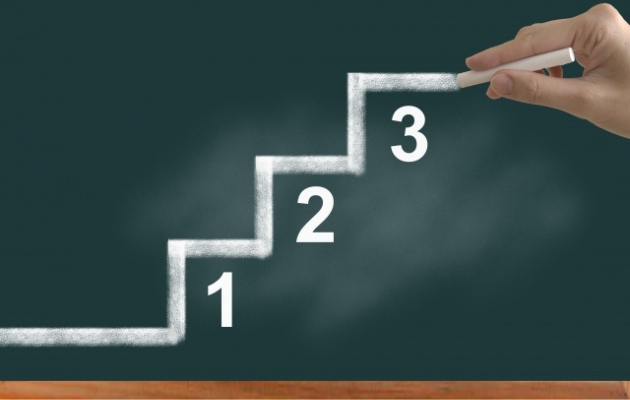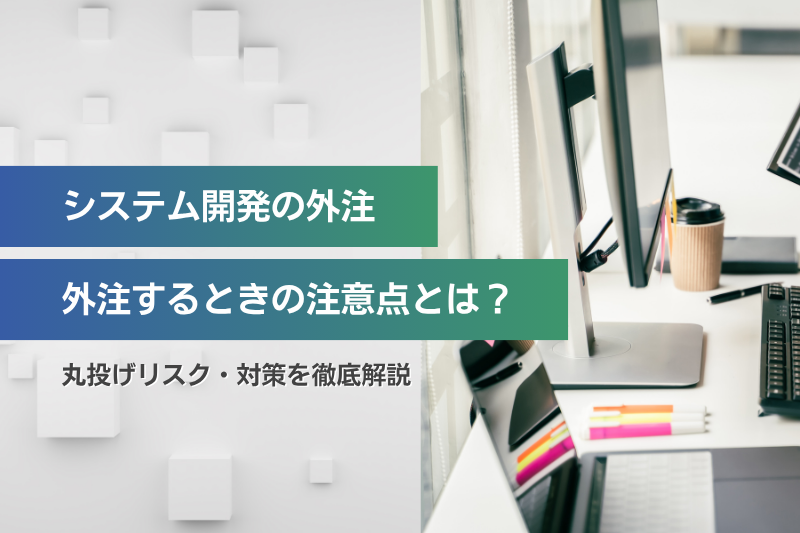3社に見積もりを依頼したら、最高で2倍の差。
「どれが正しいのか」「どこを信じるべきか」
多くの発注担当者が最初にぶつかる壁です。
しかし、正しい見積もりの見方を知っていれば、もう迷う必要はありません。
見積もりの妥当性判断は、内訳と根拠を確認する「正しい見方」を知るだけで可能です。
この記事では、開発受託のプロが見積もりの内訳項目から、妥当性を判断する5つのチェックポイントを徹底解説します。
最後まで読めば、自信を持って見積もりを精査し、社内稟議を通せるようになるでしょう。
記事監修者

DX開発パートナーは、20年以上の実績を持つリーダーを中心に、
多様なバックグラウンドを持つ若手コンサルタント、PM、エンジニアが連携するチームです。
柔軟で先進的な発想をもとに、DXの課題発見からシステム開発・運用までを一貫して支援しています。クライアントの「DX・システム開発」に関する課題やお悩みをもとに、役立つ情報を発信しています。
【徹底解剖】システム開発の見積書の内訳と妥当性

システム開発に含まれる主な費用の内訳は以下のとおりです。
- 要件定義費
- 設計費(基本/詳細)
- 開発費(製造)
- テスト費
- プロジェクト管理費(PM費)
- 保守・運用費
主要な6つの内訳項目と、それぞれの費用の目安について、開発受託チームの視点から詳しく解説します。
以下が費用内訳の早見表です。参考にしてください。
| 項目 | 役割 | 目安比率 | よくある落とし穴 | 確認質問(発注側) |
| 要件定義 | 目的・要件の確定 | 6%~10% | すり合わせ不足→手戻り | 「要求・制約・非機能の抜けはありませんか?成果物は要件定義書+業務フロー+データ定義まで含みますか?」 |
| 基本/詳細設計 | 外部/内部設計 | 34% | 画面だけ確定・内部曖昧 | 「API・ERD・例外系まで明文化されていますか?受入観点表は誰が作成し合意しますか?」 |
| 開発(製造) | 実装 | 33% | 人月定義が曖昧 | 「人員×期間×稼働率=合計人月は見積の人月と一致しますか?レビュー基準は?」 |
| テスト | 品質担保 | 33% | ケース不足・短縮 | 「単体/結合/総合/受入の責任分担は?不合格時の再テスト費用は?」 |
| PM(管理) | 進捗/品質/課題管理 | 10%~15% | 「一式」で実態不明 | 「体制表(ロール/稼働率)は?課題・変更管理プロセスは文書化されていますか?」 |
| 保守・運用 | 障害/更新/運用 | 年間5%~15%(開発費比) | 範囲未定義・時間外 | 「SLA(応答/復旧)・時間外料金は?対象外作業は何ですか?」 |
※設計・開発・テストの比率は「開発工程=100%」の内訳です。要件定義・PM・保守運用は別枠の加算であり、合算で100%にする設計ではありません。
要件定義費|プロジェクトの土台作りにかかる費用
要件定義は、システム開発の中でも最も重要な工程の一つです。業務課題の整理、機能設計、データ構造や運用フローの明確化などを行い、プロジェクト全体の方向性を決定します。
多くの開発会社では、要件定義費を開発工程(設計・開発・テストの合計)費用の6%~10%を目安として算出するのが一般的です。
要件定義では専門知識を要するため工数が大きくなりますが、精度の高い要件定義によって、後工程での手戻りや追加費用を防げます。
例えば、開発工程(設計~テスト)の合計が500万円の開発では、30万円から50万円が目安です。
設計費(基本/詳細)|システムの設計図作成費用
設計費は、開発工程(設計~テスト)における工数の約34%が適正な目安とされ、開発の品質を左右する重要工程です。設計工程では、要件定義書を基にシステムの構造を明確化します。
基本設計で画面レイアウトや操作方法を定め、詳細設計で内部の動作やデータ処理を設計します。作業内容が多岐にわたり、専門知識を持つ技術者の工数が必要になるため、一定の費用が発生するでしょう。
設計費の相場は全体の34%程度です。IPA『ソフトウェア開発分析 データ集 2022』によると、基本設計18.2%、詳細設計17.2%で、設計全体は工数の約35%。費用が全体の3割前後となります。
開発費(製造)|「人月単価」の妥当性はここで見る
開発費は開発工程(設計~テスト)における工数の33%が目安で、工数とコストが集中する主要工程です。
開発工程では、設計書を基にエンジニアがプログラミングを行い、機能を実装します。
複数の技術者が長期間関わるため、費用が大きくなります。妥当性を判断する際は、エンジニアのスキルに応じた人月単価が重要です。
人月単価は、エンジニア1人が1か月作業した場合の費用を示す指標です。
一般的なプログラマーで月60万~100万円、システムエンジニアで月80万~120万円が目安とされています。相場範囲に収まっていれば、費用は概ね適正だと言えるでしょう。
テスト費|品質担保に不可欠なコスト
テスト費は、開発工程(設計~テスト)における工数の33%を占める妥当な水準であり、品質を保証するうえで欠かせない工程です。
テスト工程では、開発されたシステムが要件定義や設計内容に沿って正しく動作するかを検証します。
バグや不具合を早期に発見することで、リリース後の障害や改修コストを防止できます。品質を維持するためには、十分なテスト工数が必要です。
費用の相場は全体の33%程度です。機能が複雑なシステムほどテスト項目が増えるため、費用も上昇します。
相場より極端に低い見積もりは、検証工程が不足している可能性があり、品質リスクにつながります。
プロジェクト管理費|見落としがちな進行管理コスト
プロジェクト管理費は、開発工程費用(設計~テスト)に対する10%~15%を占める水準であり、進行と品質を安定させるために不可欠な費用です。
プロジェクト管理費には、進捗管理、品質管理、課題管理などを担うプロジェクトマネージャー(PM)の人件費が含まれます。
PMは開発全体を統括し、スケジュール遅延や品質低下を防ぐ役割を担います。適切な管理体制を整えることで、開発の効率を高め、安定した成果を維持できるでしょう。
見積もりを確認する際はPMやPMOの人数、関与時間などが明記されているかを確認すると、費用の妥当性を判断しやすくなります。
保守・運用費|開発後にかかるランニングコスト
保守・運用費は、開発費の年間5%~15%を占める水準であり、システムの安定稼働を維持するために不可欠な費用です。
保守は、障害対応やOS・ミドルウェアの更新対応など、システムの継続利用を支える業務を指します。運用は、データ監視や日常的なオペレーション代行など、運営を安定させる作業を含みます。
リリース後も継続的に作業が発生するため、一定のコストが必要です。
費用の目安は、開発費の年間5%~15%程度になります。例えば、1,000万円で開発したシステムでは年間50万円~150万円が一般的な水準です。
契約時には、対応範囲を明確にし、見積もりの根拠を確認してください。
システム開発の見積算出方法

システム開発の見積もりは、開発会社が用いた算出方法によって金額や精度が変わってきます。
システム開発で主に使われる見積もりの算出方法は以下のとおりです。
- トップダウン見積
- ボトムアップ見積
- パラメトリック見積
プロジェクトの段階や目的に応じて使い分けられるため、それぞれの特徴を知ることが、妥当性判断の第一歩と言えるでしょう。
トップダウン見積(類推見積)
トップダウン見積は、過去に実施した類似プロジェクトの実績を基に、全体の開発費用を大まかに算出する方法です。初期段階で概算を把握したい場合に適しています。
過去の開発実績を参照することで、要件定義や設計が固まっていない段階でも、予算の目安を迅速に提示できます。社内の稟議や予算計画を立てる際に、早い段階で金額感を把握できることが、発注担当者にとっての大きな利点です。
トップダウン見積はスピード面で優れていますが、精度が低く、参考となる過去データがない場合には適用が難しい方法です。正式な見積もりを行う前の参考情報として活用するようにしましょう。
ボトムアップ見積(工数積み上げ)
ボトムアップ見積は、開発に必要な作業を細かく分解し、それぞれの工数と単価を積み上げて全体費用を算出する方法です。現在最も一般的で、精度の高い見積もり手法とされています。
作業内容をWBS(Work Breakdown Structure:作業分解構成図)によって詳細に洗い出し、工程ごとに必要な時間と単価を掛け合わせて積算します。
作業単位で見積もりを行うため、作業の抜け漏れが少なく、根拠が明確な見積もりを提示できる点が大きな特徴です。
ボトムアップ見積は精度が高い一方で、作業の分解と工数算出に時間がかかるため、要件定義や設計内容が固まった段階での利用が適しています。
詳細見積もりの際には、ボトムアップ見積が採用されているかを確認しましょう。
パラメトリック見積
パラメトリック見積は、過去の開発データや統計情報をもとに、一定の「パラメータ(要因)」を使って費用を算出する方法です。
トップダウン見積よりも客観性が高く、短時間で概算を出したい場合に適している手法です。
開発規模や画面数、機能数、行数、ステップ数といった定量的な要素を基準に、過去プロジェクトの実績データを分析して単価や係数を設定します。
例えば「1画面あたりの平均開発コスト」や「1機能あたりの平均工数」をもとに、全体の費用を推定します。データに基づくため、再現性が高く、見積もりのばらつきを抑えられる点が特徴です。
一方で、正確な過去データや統計モデルが整備されていない場合には、精度が下がるという課題があります。
開発会社が過去のデータを蓄積・分析して見積精度を高めているかも、信頼性を見極めるポイントです。
システム開発の見積もりの妥当性を判断する5つのチェックポイント

システム開発の見積もりの妥当性を判断するためにチェックすべきポイントは以下の5つです。
- 作業範囲(スコープ)は明確に定義されているか?
- 工数(人月)は過大または過小に見積もられていないか?
- エンジニア単価は業界相場と乖離していないか?
- 前提条件(体制・期間・環境)に認識のズレはないか?
- リスク(バッファ)は適切に考慮されているか?
妥当性を判断するチェックポイントを知ることで開発会社の言いなりにならず、対等な立場で交渉を進められるようになるでしょう。
作業範囲(スコープ)は明確に定義されているか?
見積もりの妥当性を判断する際は、作業範囲(スコープ)が明確に定義されているかを最初に確認することが重要です。
スコープの定義が不十分な場合、見積金額の根拠を正確に判断できません。
対象業務の範囲があいまいなまま契約すると、契約後に「見積もり対象外の作業」として追加費用を請求されるリスクが高まります。
見積書には、作業の対象となる範囲と、対象外となる範囲を明確に記載してもらう必要があります。
作業範囲を具体的に整理することで、発注内容と金額の妥当性を正しく判断できるでしょう。
スコープの明確化は、見積もりの妥当性を判断するうえで最も基本的かつ重要な確認項目です。
工数(人月)は過大または過小に見積もられていないか?
見積もりの妥当性を判断するためには、提示された工数(人月)が適切であるかを確認する必要があります。
工数は見積金額の基盤です。設定が多すぎれば費用が膨らみ、少なすぎれば品質の低下や納期の遅延を招き、最悪の場合はプロジェクトが破綻します。
工程別の費用割合(例:開発費33%)と、見積もり内の工数配分を比較し、偏りの有無を確認することが重要です。
機能単位で工数が多い場合は、根拠資料としてWBS(作業分解構成図)の提示を求め、内容を精査しましょう。
エンジニア単価は業界相場と乖離していないか?
見積もりの妥当性を判断する際は、提示されたエンジニア単価(人月単価)が業界相場と比較して適切かを確認することが重要です。
単価が高すぎればコストの無駄につながり、安すぎればスキルや経験が不足した人材が担当する可能性があり、品質面でのリスクが生じます。
システムエンジニアの相場は月80万円~120万円です。
相場から大きく外れた単価が提示されている場合は、理由や根拠を必ず確認する必要があります。
単価の妥当性を確認することは、コスト構造の透明性を高め、プロジェクト品質を確保するうえで欠かせないポイントです。
前提条件(体制・期間・環境)に認識のズレはないか?
見積もりの妥当性を判断する際は、見積書の末尾に記載された前提条件を熟読することが重要です。
前提条件は、条件不成立時に追加費用や納期変更を認める免責事項として機能します。
自社で実施すべき作業や負担範囲を精査し、実行不可能な要件や合意できない制約が含まれていないかを確認します。
前提条件への合意は契約への合意に極めて近い意味を持つため、解釈の相違が生じないように文言レベルで擦り合わせてください。
前提条件の整合確認は、コスト・スケジュール・品質リスクを抑えるための必須チェック項目です。
リスク(バッファ)は適切に考慮されているか?
見積もりの妥当性を判断する際は、リスク(バッファ)が適切に含まれているかを確認してください。システム開発では、予期せぬトラブルや課題が発生することが多く、リスク対応を考慮していない見積もりは危険です。
PMIの資料ではITサービス案件で15~25%を固定率で積む手法が紹介されており、ソフトウェア開発の例として20%を用いるケースも示されています。
バッファがまったくない見積もりは、軽微な仕様変更やトラブルでも即座に追加費用や納期遅延が発生する可能性があります。
一方で、過剰なバッファは不当なコスト増加につながるため、妥当な範囲で設定されているかを見極めることが必要です。
リスクを考慮した適切なバッファの有無を確認することは、見積もり全体の信頼性を判断するうえで欠かせない視点です。
「高すぎる見積もり」と「安すぎる見積もり」の正体

5つのチェックポイント(スコープ、工数、単価、前提条件、リスク)を分析すると、見積もり金額が高額または低額と判断される場合があります。
ただし、金額の大小だけで判断するのは危険です。価格差には必ず要因があり、背景を理解することで、より正しく判断できるでしょう。
以下では、相見積もりで提示された高額見積もりと低額見積もりの要因を整理し、発注判断に必要な視点を解説します。
見積もりが高すぎないか?
相見積もりを取った際に、「高すぎる」見積もりが出てくるのには必ず理由があります。
単純に利益を多く乗せている場合もありますが、多くは「高い技術力や品質管理体制の裏付け」か、「発注側の要求が曖昧すぎるための過剰なリスク回避」のどちらかです。
例えば、RFP(提案依頼書)が曖昧だと、開発会社は不測の事態に備えて工数を多めに積まざるを得ません。
一方で、高度なセキュリティ要件や大規模なアクセスに耐えうるシステムなど、高い技術力が求められる場合も金額は上がります。
見積もりが高い理由を突き詰めれば、相手の技術力やプロジェクトへの理解度を見極められます。
見積もりが安すぎないか?
発注担当者として最も注意すべきは、「高すぎる」見積もりよりも「安すぎる」見積もりです。
安いのには必ず裏があり、多くは「必要な工程(特にテスト)の大幅な省略」や「スキルや経験の浅い人材の投入」に起因します。
相場より極端に安い場合、最初は安価に受注し、プロジェクトが始まった後で次々と「追加費用」を請求する算段である可能性も否定できません。
また、テストが不十分なまま納品され、リリース後に障害が多発してビジネスが停止するリスクもあります。金額の安さだけで選定することは、プロジェクト失敗への最短ルートだと心得ましょう。
システム開発の見積もりの妥当性に関してよくある質問

Q:要件定義が明確でない状態でも見積もりを依頼して問題はありませんか?
要件が固まっていない段階では、概算見積(トップダウン見積またはパラメトリック見積)を依頼することが可能です。
要件が未確定な段階で提示される見積もりは、精度が低い点に注意してください。正式な金額ではなく概算であることを理解し、要件定義フェーズ完了後に改めて精緻な見積もりを求めるようにしましょう。
初期段階から詳細な見積もりを求めると、開発会社が不確定要素に備えてリスク工数を上乗せする場合があります。
予算感を把握したい場合は、概算見積を活用し、要件定義後に精度の高い見積もりを取得する流れが適切です。
Q:見積書に「一式」と記載されている場合、問題がありますか?
「一式」という表記には注意が必要です。「一式」は作業範囲を明確に定義せず、複数の作業や成果物をまとめて金額を算出している状態を表します。
作業範囲が不明確なまま契約を締結すると、契約後に「見積範囲外の作業」と判断され、追加費用が発生するおそれがあります。
「一式」と記載された項目は、作業内容・成果物・範囲外作業を明文化して提示してもらうことが重要です。
特に「データ移行一式」や「テスト一式」といった項目は、解釈の幅が広く誤解が生じやすいため、契約前に詳細を確認する必要があります。
Q:発注後に見積金額が増加するのはどのような理由によるものですか?
見積金額が増加する主な要因は、要件変更と前提条件の不一致です。
見積もり時点で想定していなかった仕様変更が発生した場合や、発注側が準備する予定であったデータや作業環境の整備が遅れた場合には、追加工数が発生します。
契約前に、要件変更や追加対応時の費用算定ルールを文書で定義しておくことが重要です。
変更管理の取り決めを明確にしておくことで、金額に関する認識のずれを防ぎ、トラブルの発生を抑えられます。
Q:契約形態(請負/準委任)は金額にどう影響しますか?
契約形態は、費用の考え方とリスクの所在に直結します。
請負契約は、成果物の完成を目的とします。開発会社は完成責任を負うため、予期せぬトラブルに備えて一定のリスクを工数に含めるのが一般的です。
要件が明確な場合に適していますが、リスクを工数に乗せる分、見積もり金額は高めになる傾向があります。
準委任契約は、作業時間を提供することを目的とします。開発会社は完成責任を負いません。
リスクは発注者側が負担するため、バッファが乗らない分だけ人月単価が請負より安く見える場合があります。要件が不明確な場合やアジャイル開発では準委任が選ばれやすいです。
Q:開発手法(アジャイル/ウォーターフォール)で見積もりは変わりますか?
開発手法によって見積もりの「出し方」と「性質」が大きく変わってきます。
「ウォーターフォール開発」は、開発開始前にすべての仕様を確定させるため、ボトムアップ(工数積み上げ)で見積もりを算出しやすく、初期段階で総額見積もりを提示しやすい手法といえます。
一方、「アジャイル開発」は仕様の変更を前提に、短期間の開発サイクル(スプリント)を繰り返す手法です。
アジャイル開発では全体像が見えにくい特性上、初期段階での総額見積もりが難しく、スプリント単位での契約や概算見積もりとなるケースが一般的です。
Q:見積もりの「人月」って、実際どういう意味ですか?
「人月(にんげつ)」とは、1人のエンジニアが1か月間フル稼働した場合の作業量を指します。例えば「3人月」とは、エンジニア3名が1か月間作業する、または1名が3か月間作業する量に相当します。
ただし、実際の稼働率は常に100%ではありません。一般的に80~90%程度を想定し、休暇・打ち合わせ・調整期間(バッファ)も含めて見積もられます。
見積もり金額の妥当性を確認する際には、1人月を何時間で算定しているのか、稼働率を何%で見積もっているのかを必ず確認することが大切です。
前提条件を具体的に把握することで、見積もり内容の信頼性と比較の正確性が高まります。
Q:相見積もりは何社取るのがベストですか?
結論として、3社が最も現実的で効果的な数と言えます。
1社だけでは、その見積もりが妥当かどうかの比較対象がありません。
逆に、5社や6社とあまりに多く取りすぎると、RFPの説明や質疑応答、提案の比較検討にかかる発注者側の工数が膨大になり、現実的ではありません。
3社あれば「高すぎる会社」「安すぎる会社」「平均的な会社」というように、金額の「軸」と「相場観」を把握することが可能です。
大切なのは単なる金額比較ではなく、RFPへの理解度や提案内容の質を比較することです。
Q:見積もり金額を下げる交渉はできますか?
見積もり金額の調整は可能ですが、単価を下げる交渉よりも「作業範囲(スコープ)の見直し」のほうが効果的です。
単価を無理に下げると、担当者の稼働時間や品質管理にしわ寄せが生じ、結果的に品質リスクが高まる恐れがあります。
一方で優先度の低い機能を次フェーズに回すスコープ調整や、発注側で対応できる作業を明確にすれば、実質的に見積もりを圧縮できます。
「費用を下げる=品質を落とす」ではなく、要件を整理し、リスクを最小化する交渉が妥当なコスト削減につながるでしょう。
まとめ|妥当な見積もりを見抜き、プロジェクトを成功に導くために
今回は、システム開発見積もりの妥当性を判断する方法を、内訳項目と5つのチェックポイントを通して解説しました。
システム開発の見積もりの妥当性を判断する5つのチェックポイントは以下のとおりです。
- 作業範囲(スコープ)は明確に定義されているか?
- 工数(人月)は過大または過小に見積もられていないか?
- エンジニア単価は業界相場と乖離していないか?
- 前提条件(体制・期間・環境)に認識のズレはないか?
- リスク(バッファ)は適切に考慮されているか?
見積もりは“金額”ではなく“根拠”で判断することが大切です。内容を一つずつ精査し、開発会社と対等に議論できるようになれば、プロジェクト成功の確率は格段に上がります。
信頼できる開発パートナーをお探しの方は、まずはご相談ください。見積書の比較やRFP作成支援も無料でサポートしています。迷ったときは、第三者の専門家に相談するのが最短です。
お問い合わせフォームでは「DX開発パートナーズ」をお選びください