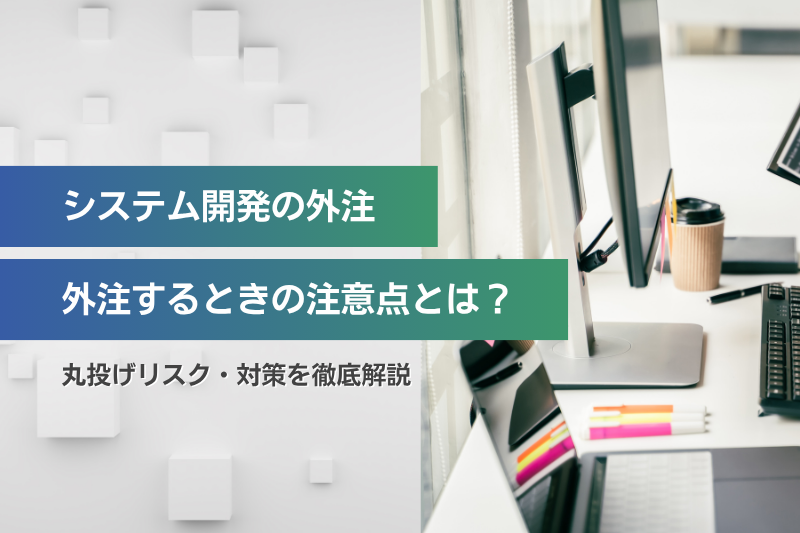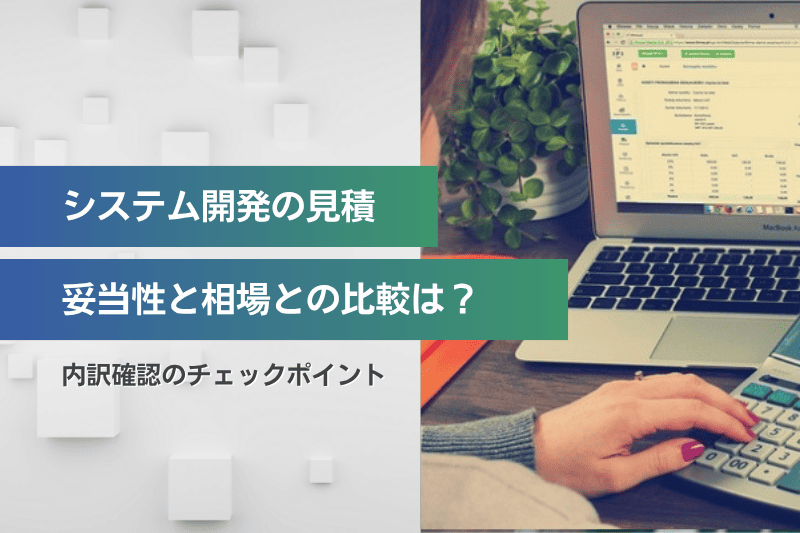「システム開発を依頼したいものの、大手以外で信頼できる会社が見つからない。」
「信頼できる開発会社を探しても、違いが見えず判断に迷う。」
同様の悩みを抱える企業は多いのではないでしょうか。
システム開発は、規模によっては500万円以上の投資になります。一度の発注ミスが、予算超過や機会損失につながるケースも少なくありません。
システム開発発注の成功は「全流れ」の理解と「戦略的パートナー」の見極めが鍵です。
この記事では、開発受託のプロが、発注の全7ステップと、失敗しない開発会社の合理的な選定基準5選を徹底解説します。
この記事を読めば、システム開発の費用対効果を最大化し、自社の課題を解決する最適なパートナーを自信を持って選定できるようになるでしょう。
記事監修者

DX開発パートナーは、20年以上の実績を持つリーダーを中心に、
多様なバックグラウンドを持つ若手コンサルタント、PM、エンジニアが連携するチームです。
柔軟で先進的な発想をもとに、DXの課題発見からシステム開発・運用までを一貫して支援しています。クライアントの「DX・システム開発」に関する課題やお悩みをもとに、役立つ情報を発信しています。
【全流れ】システム開発発注の7ステップ
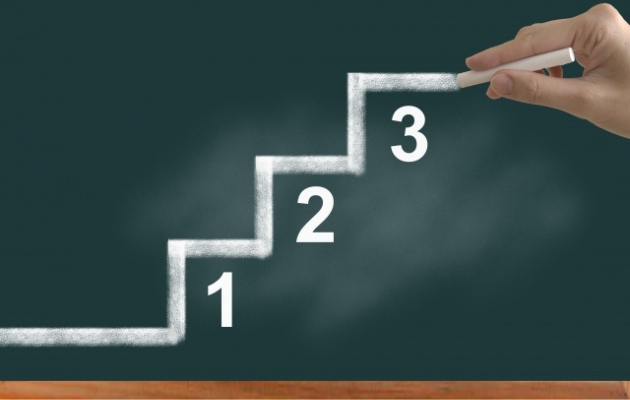
一般的にシステム開発プロジェクトは計画どおりに進まない事例が多いとされています。
要件定義の不備や仕様変更が原因で、予算超過・納期遅延・品質未達に至る事例も少なくありません。
プロジェクト失敗の主な原因は、発注担当者がシステム開発発注の全工程を十分に理解していないことにあります。
本章ではプロジェクトの主導権を握り、失敗確率を大きく下げるためにシステム開発の7つのステップを開発受託のプロの視点から解説します。
Step1:企画・構想
システム開発の最初の重要なステップは「システムをなぜ作るか」という目的を明確にすることです。経営上のボトルネックを見つけ、システム投資によって削減できるコストを明確にしてください。
経営課題を的確に見つけ出さなければ、システム開発の成功確率は大幅に低くなります。
実際に特定非営利活動法人IT整備士協会の分析では、IT導入の失敗要因として「経営戦略との不一致」が主要因の一つに挙げられています。
明確な戦略を持たないシステム投資は、成果につながらない高額な支出になりかねません。
「なぜ作るのか」という目的が明確であるほど、開発会社の選定や要件定義の段階で、合理的な判断ができるでしょう。
ただ、発注担当者だけで経営課題を完璧に言語化するのは困難です。だからこそ「開発会社選び(Step3)」が重要です。優れたパートナーであれば、この企画段階から課題整理を伴走してくれます。
Step2:RFP(提案依頼書)作成
経営課題を言語化できたら、「RFP(提案依頼書)」に落とし込みます。
RFPとは、システム開発会社に対し自社の課題や要望を伝え、解決策の提案を正式に依頼するための書類です。
失敗するシステム開発では、RFPに導入したい機能一覧だけを載せているケースが多いです。機能一覧しか含まれていないRFPでは、各社の提案内容に差が出にくく、発注側は最終的に価格だけで比較・判断せざるを得ません。
成果につながるRFPでは「開発の背景」「現状の課題」「達成したいゴール」を明確に示します。
経営課題や目的が明確であればあるほど、開発会社は経営課題の解決に最適な提案をしやすくなります。費用対効果の高い開発や、長期的な運用を見据えた提案につながるでしょう。
Step3:開発会社選定・見積比較
RFPを複数の会社(通常3社〜5社)に送り、提案と見積もりを受け取ります。開発会社の選定が発注プロセスにおける最大の難関であり、最も悩む部分でしょう。
「大手SIerは安心だが高すぎる」「安いベンチャーは信頼できるか不安だ」「各社で見積もり金額がバラバラで比較できない」このような悩みは当然です。
開発会社は、絶対に価格だけで判断してはいけません。システム開発の見積もりは「作業時間 × 単価」で決まります。
安い見積もりには「品質が低い」「リスクを見積もっていない」「実は下請けに丸投げしている」などの理由がある場合が多いです。
開発会社選びで後悔しないためにも、次の見出し「システム開発の発注で失敗しない会社選びの合理的基準5選」をぜひ参考にしてください。
Step4:要件定義
パートナーとなる開発会社が決まったら、要件定義を行いましょう。
多くの発注担当者が要件定義を開発会社任せにしがちですが、実は要件定義こそがパートナーの理解力や提案力が最も表れるフェーズです。
要件定義は、発注側と開発会社が共同で行う最も重要な作業です。要件定義を発注側が主導できないと、開発終盤での仕様変更や追加費用、納期遅延につながります。
実際にIPA(情報処理推進機構)の調査では、システム開発のトラブル原因の多くが要件定義に起因していると報告されています。特に、遅延の過半数は要件定義の誤りによるものであり、「Step3:会社選び」の失敗とも言えるでしょう。
優れたパートナーは、発注者の曖昧な要望を鵜呑みにせず、業務フローを深くヒアリングし、プロの視点で要件を整理・主導してくれます。
要件定義を成功させるためには、発注側が業務を整理する努力と、業務整理したものをシステムに落とし込むパートナーの提案力・主導力が不可欠です。
Step5:設計・開発・テスト
要件定義ができると、開発会社は「設計」「開発」「テスト」と業務を進めます。
開発の進め方にはいくつかの代表例があり、要件の固まり具合・変更頻度・納期によって最適解が異なります。
| 開発手法 | 特徴 | 向いているケース |
| ウォーターフォール開発 | 工程を順番に進める手法。進行管理がしやすい一方、途中変更に弱い。 | 業務要件が固まっている基幹・業務システム |
| アジャイル開発 | 少ない機能に絞り短サイクルで開発と検証を繰り返す。変更に強くスピード重視。 | 仕様が動く新規サービス、概念実証(PoC) |
| プロトタイプ開発 | 早期に試作品を作り、発注側の確認・改善を重ねる。ユーザー体験を具体化しやすい。 | UI/UX重視、関係者合意形成が必要 |
| スパイラル開発 | 重要機能から段階的に作り上げ統合していく。大規模・複雑案件に向く。 | 大規模・複雑システム |
システム開発の業務自体は開発会社に任せますが、週1回の定例ミーティングを設け、進捗を確認することが重要です。
特にアジャイル開発(短期間で開発とレビューを繰り返す手法)を採用する場合、発注側はデモを頻繁にレビューし、フィードバックする責任があります。
テスト段階で「イメージと違う」というズレを早期に発見・修正することが、手戻りによる追加コストを防ぐ最大のコツです。
Step6:受け入れ(検収)
システムが完成したら、納品前の最終チェックである「受け入れ(検収)」を行います。
受け入れは、RFPや要件定義書で合意した内容がすべて満たされているかを、発注側が確認する作業です。
受け入れの際に確認すべきは、バグの有無だけではありません。
実際の業務フローに沿ってデータが正しく処理されるか、一般社員がマニュアルなしでも直感的に操作できるかなど、利用者の視点で丁寧にテストすることが重要です。
要件定義書と異なる部分が見つかった場合は、受け入れ段階で修正を依頼してください。「検収完了」と署名した後に修正を求める場合、追加費用が発生します。
追加費用を防ぐためには、実際の業務で利用する場面を想定しながら、開発されたシステムを丁寧に確認することが効果的です。
Step7:運用・保守
システム開発を成功させるには、開発費だけでなく、運用・保守にかかるコストを含めて判断することが重要です。システムは「作って終わり」ではなく、納品後の運用からが本当のスタートになります。
開発会社とは必ず「運用・保守契約」を締結し、運用・保守契約の内容を開発契約と併せて確認する必要があります。
確認すべき項目は以下のとおりです。
- 障害が発生した際、何時間以内に対応してくれるのか。
- 「軽微な修正(例:ボタンの色を変更するなど)」は保守費用に含まれるのか。
- サーバー代や、ミドルウェアのライセンス料は誰が負担するのか。
保守費用の内訳を確認せずに契約を進めた結果、開発費は抑えられたものの、運用コストが想定の3倍に膨らんだという中小企業のケースもあります。
運用・保守コストを事前に把握することが、システムを長期的に安定運用するための第一歩です。
システム開発の発注で失敗しない会社選びの合理的基準5選

システム開発発注の全流れの中で、プロジェクトの成否を9割決めるのが「開発会社選び」です。
中小企業の決裁者の多くが「大手SIerは信頼できるが高すぎる」「一方で、安価な無名の会社は品質や体制が不安で安物買いの銭失いになりそうだ」といったジレンマに陥ります。
検索しても各社の違いはわからず、何を基準に選べばよいか途方に暮れてしまうのも無理はありません。
開発受託のプロである筆者の視点から、中小企業が「費用対効果」と「信頼性」を両立させるパートナーを見極めるための合理的な選定基準を5つ具体的に解説します。
基準1:課題解決(戦略)の「提案力」があるか
開発会社が、自社の課題を的確に理解し、解決策を提案できるパートナーであるかを確認してください。
初回の打ち合わせで、発注者の話をただ聞くだけの姿勢を見せる会社には注意が必要です。
優れた開発パートナーは、「なぜその機能が必要なのか」「その課題であれば、既存のSaaSと連携するほうがコストを抑えられないか」を問い、既存SaaSの活用なども含めて課題解決を最適化します。
すぐに見積書を提示しようとする会社には注意が必要です。「はい、作れます」と技術的な可否だけで即答する会社は、課題の本質を見落とす可能性があります。
一方で、真のパートナーは「まず、業務フローを拝見させてください」と依頼し、課題の構造を正確に把握することから始めます。
システム開発におけるパートナー選定では、技術力そのものよりも、課題を理解し最適な解決策を導ける提案力を重視することが重要です。
基準2:自社の課題・規模と一致する実績があるか
開発会社の実績に自社と類似した案件があるかを確認することも重要です。
多くの会社がWebサイトに「実績多数」と掲載していますが、数に惑わされてはいけません。
例えば、従業員50名規模の製造業が基幹システムを発注する際に、実績が大企業やスタートアップ向け案件に偏る会社へ依頼すると、要件やコスト面でミスマッチが生じやすくなります。
大企業向けの会社では仕様が過剰になりコストが膨らみ、スタートアップ向けの会社では業務やセキュリティ要件を理解できず、プロジェクトが混乱する恐れがあります。
開発会社を選定する際は、「同業界」「同規模」「同様の経営課題」を持つ企業のシステムを手がけた実績があるかを確認してください。
類似案件の実績を持つ会社こそが、発注企業の業務を理解し、現実的かつ効果的なシステムを構築できる信頼性の高いパートナーです。
基準3:開発体制とコミュニケーションの透明性が担保されているか
システム開発を依頼する前に必ず開発体制を確認してください。
大手SIerの見積もりが高くなる背景には、多重下請け構造があります。
元請けが案件を受け、実際の開発を下請け・孫請けに委託するため、情報伝達のズレと中間マージンの積み重ねでコストが増えるのです。
打ち合わせの際に「実際の開発担当者は、打ち合わせに同席可能ですか?」と質問してみてください。
営業やPMのみで開発者の同席を渋る場合、社内に実装部隊が薄いか多重下請けの可能性が高いと判断できます。
また、開発体制だけでなくコミュニケーションの透明性も重要です。進捗報告の頻度や共有ツール、意思決定のプロセスが明確であれば、認識のズレや手戻りを防ぎ、トラブルを未然に防げます。
コミュニケーションがスムーズで、開発体制が透明であることは、品質とコストの適正化に直結する重要な判断基準です。
基準4:見積もりの「内訳(人月単価と工数)」は適切か
複数社からの見積もりを総額だけで比較しがちですが、内訳も必ず比較してください。
システム開発の見積もりは、基本的に「工数(人月)× 人月単価」で算出される仕組みです。
例えば、総額600万円でも「A社:100万円/月 × 6ヶ月」と「B社:150万円/月 × 4ヶ月」では意味が全く違います。B社は月当たりの単価が高く、短期間で開発できる技術力があると読み取れます。
見積もりに「一式」とだけ記載されている場合は、注意が必要です。各機能や工程に対して、どれくらいの工数を想定しているのかを明確にしてもらいましょう。
提示された工数の妥当性を比較・確認することで、費用と効果のバランスを合理的に判断できます。
基準5:契約形態を比較検討してくれるか
システム開発の契約には「請負契約」と「準委任契約」の2種類があり、責任範囲が大きく異なります。
契約形態を一方的に提示する会社ではなく、プロジェクトの目的やリスクを踏まえて両者を比較検討してくれる会社を選ぶことが重要です。
請負契約は、成果物の完成を約束する契約で、見積金額を確定しやすい点がメリットです。ただし、要件定義後の変更は原則すべて追加費用となります。
一方、準委任契約は作業時間に応じて費用が発生し、仕様変更に柔軟に対応できる反面、長期化によるコスト増に注意が必要です。
プロジェクトの性質に合わせ、確実性重視なら請負契約、柔軟性重視なら準委任契約が適切です。違いを理解しないまま進めると、仕様変更時の高額請求など契約起因のトラブルに直結します。
システム開発の発注で費用を適正化する4つのコツ

システム開発は、中小企業にとって非常に高額な投資です。
「できるだけ費用を抑えたい」と考えるのは当然ですが、単なる「値切り」は、品質の低下や開発会社のモチベーション低下に直結し、プロジェクト失敗の原因となります。
目指すべきは「コスト削減」ではなく「コストの適正化」です。
本章では、開発費用を適正化するための4つの実践的なコツを解説します。
見積書の中身を可視化し根拠のある金額を引き出す
システム開発の見積もりを正しく判断するためには、金額そのものよりも「中身(根拠)」を確認することが重要です。
見積書に「一式」とだけ記載されている場合、作業範囲が曖昧なまま金額が算出されている可能性があります。
機能や画面ごとの工数を明示してもらうことで、どこにどれだけの作業が発生しているのかを把握できます。
バッファ(予備工数)の設定や、保守費用に含まれるSLA(Service Level Agreement:サービス品質保証契約)を確認すれば、見積もりの妥当性を見極めやすくなるでしょう。
交渉の本質は価格の切り下げではなく、根拠の可視化と妥当性の確認です。
要件定義を明確にし「無駄な仕様変更」を減らす
システム開発を依頼する前の段階で要件定義を明確にし、無駄な仕様変更を減らすことが重要です。
システム開発では、開発途中の仕様変更が予算超過の大きな要因の一つとされています。
最も効果的なコスト削減策は、開発前の要件定義の段階に、発注側が十分な時間とリソースを投資することです。
「必ず実装すべき機能(Must)」と「実装できれば望ましい機能(Want)」を明確に切り分け、開発範囲を確定させることで、無駄な追加費用を防げます。
MVP(最小構成)でスタートし小さく育てる発想を持つ
システム開発では、最初からすべてを作ろうとせず、MVP(Minimum Viable Product:最小限の機能を持つ製品)で始めることが最も効果的です。
多くの中小企業では、「せっかく投資するなら最初から完璧なシステムを作りたい」という発想に陥りがちです。
しかし、機能を詰め込みすぎると開発期間の延長やコスト増につながるだけでなく、利用されない機能が増加する傾向があります。
MVP開発では、まず最も重要な経営課題を解決する1つのコア機能だけを実装することが基本です。
実際に現場で運用しながらフィードバックを得て、必要な機能だけを後から段階的に追加することで、ムダのないシステムを構築できます。
「小さく始めて、大きく育てる」考え方は、初期投資を最小限に抑えつつ、ROI(投資対効果)を最速で実現する発注戦略です。
既存SaaSやローコードとの使い分けを相談する
システム開発は、すべてをゼロから作る時代ではありません。既存のSaaSやローコードツールを活用し、独自性が必要な部分だけをオーダーメイドで開発することが、最も効率的です。
近年は、安価で高機能なSaaSや、短期間で開発できるローコード・ノーコードツールが数多く登場しています。
既存のSaaSやツールを上手に活用することで、コストを抑えながらスピーディに業務システムを構築できます。
例えば、勤怠管理・経費精算・顧客管理といった業界共通の標準業務は、既存のSaaSを導入してAPI連携でつなぐほうが良いでしょう。
一方で、企業独自の強みや競争力の源泉となる業務プロセスは、オーダーメイドで設計・開発する価値があります。
「どこをSaaSで代替し、どこを独自開発すべきか」を提案できる開発会社こそ、信頼できる戦略的パートナーです。
システム開発発注におけるよくある質問

Q:見積もりが各社バラバラで比較できません。どうしてこんなにバラバラなんですか?
A:見積もり金額が大きく異なる場合は、前提条件(RFP)が曖昧である可能性が高いです。まずは各社の工数と単価を確認し、見積もりの内訳を比較してください。
RFP内で要件や開発範囲の定義が不十分な場合、各ベンダーが異なる前提で見積もりを作成します。前提条件の違いが金額差を生み出す主な要因です。
見積もりを正しく比較するためには、前提条件の整理が重要です。RFPの内容を明確にし、工数と単価の内訳を照らし合わせることで、適正な判断が可能になります。
Q:システム開発の発注では、相見積もりを何社に依頼すべきですか?
A:相見積もりの依頼先は、3〜5社程度が最も適切です。
数が少なすぎると比較の精度が下がり、多すぎると情報整理に時間がかかり、判断が難しくなります。
よくある失敗は、「とにかく多くの会社に依頼すれば安心」と考えてしまうことです。
社数を増やしても、RFP(提案依頼書)の前提条件が曖昧なままでは、各社が異なる想定で見積もりを出してしまい、比較そのものが成立しなくなります。
重要なのは金額だけでなく、見積もりの根拠・提案内容・開発体制の透明性を比較することです。
費用の妥当性だけでなく、担当者の説明や質問への対応姿勢を見ることで、信頼できる開発パートナーをより正確に見極められます。
Q:契約書で特に注意すべきポイントはありますか?
A:システム開発契約でトラブルを防ぐためには、契約書の内容を正確に理解し、責任範囲を明確にしておくことが不可欠です。
契約段階の確認不足が原因で、納品後に追加費用の請求や権利のトラブルが発生するケースは少なくありません。
特に注意すべき項目は、次の3点です。
- 成果物の著作権の帰属先(発注企業と開発会社のどちらに帰属するのか)
- 仕様変更時の費用算定ルール(どの範囲で追加費用が発生するのか)
- 検収および保守の定義(どの時点で責任が移転するのか)
上記の条項が曖昧なままだと、契約後に解釈の違いが生じ、トラブルに発展するリスクがあります。
契約書の内容に不明点がある場合は、契約締結前に弁護士やITコンサルタントなどの専門家へ確認することが望ましいです。
Q:発注後にトラブルを防ぐためのコツはありますか?
A:発注後のトラブルを防ぐうえで最も重要なのは、進捗共有の仕組みと記録の管理方法を明確にすることです。
多くのシステム開発プロジェクトでは、認識のずれや報告・連絡・相談の不足が原因で、後から責任の所在をめぐる問題が発生します。
原因の多くは、仕様書よりもコミュニケーション設計の不備にあります。
効果的な対策としては、週1回の定例ミーティングの実施や議事録・チャット履歴の保存、そして仕様変更時の書面またはチケットでの正式合意が有効です。
進捗共有と記録のルールを徹底することで、認識のずれを防止し、プロジェクトを安定的に運営できます。
Q:RFP(提案依頼書)のテンプレートはありますか?
A:RFPのテンプレート自体は多数存在します。しかし、形式だけを真似するよりも、まず解決したい課題を明確にすることが重要です。
テンプレートを使用すると、項目を埋める作業が目的化しやすく、根本的な経営課題や開発の目的が抜け落ちる可能性があります。
目的が不明確なRFPは、開発会社との認識のずれを生みやすく、最終的に費用や品質に悪影響を及ぼします。
テンプレートの利用は、課題を明確にした後が望ましいです。
まずは自社の経営課題を言語化し、その内容をもとに必要な項目を選定してRFPを作成することが、成功するプロジェクトの第一歩となります。
Q:アジャイルとウォーターフォールどちらが良いですか?
A:要件が明確に固まっている場合はウォーターフォール、開発中に柔軟な変更が必要な場合はアジャイルが適しています。
両者は手法の方向性が異なり、プロジェクトの性質によって向き・不向きがはっきり分かれるためです。
ウォーターフォールは工程を順に進めるため計画通りに管理しやすい一方で、途中の仕様変更には弱い特徴があります。
アジャイルは短いサイクルで開発と改善を繰り返すため、変化に対応しやすく、試行錯誤を前提とした開発に向いています。
結論として、どちらが優れているかではなく、どのようなプロジェクトかで選ぶことが重要です。信頼できる開発パートナーであれば、目的や状況に応じて最適な手法を提案してくれるはずです。
Q:システム納品後、保守契約を結ばないとどうなりますか?
A:保守契約を締結しない場合、障害対応や軽微な修正が発生するたびに個別で費用が発生するため、運用コストが不安定になります。
さらに、サーバーやミドルウェアのアップデートに起因する不具合への対応が行われず、システムが正常に稼働しなくなるリスクも高まります。
保守契約は単なるサポート費用ではなく、安定した運用と迅速なトラブル対応を確保するためのリスクマネジメントです。
小規模な保守プランであっても、契約を締結しておくことで、障害発生時の対応スピードや継続的なシステムの安全性を確保できます。
まとめ|システム開発発注は「信頼できる戦略パートナー」選びで全て決まる
今回は、システム開発を発注する際に知っておくべき全体の流れと、失敗しない開発会社選びの合理的基準5選を、開発受託のプロの視点から解説しました。
システム開発発注の7ステップは以下のとおりです。
- 企画・構想
- RFP(提案依頼書)作成
- 開発会社選定・見積比較
- 要件定義
- 設計・開発・テスト
- 受け入れ(検収)
- 運用・保守
システム発注の成否は価格ではなく、経営課題を理解し伴走してくれるパートナーを選べるかどうかにかかっています。
まずは、なぜシステムが必要なのかを明確にし、自社の課題に寄り添ってくれる開発会社を選びましょう。
「この記事を読んでも課題の言語化は難しい」という方もいるかもしれません。
弊社では、課題整理から提案依頼書(RFP)の作成までを無料でサポートする「壁打ち相談」を実施しています。
まだ発注先が決まっていなくても構いません。まずは課題の棚卸しからご一緒に進めましょう。
お問い合わせフォームでは「DX開発パートナーズ」をお選びください